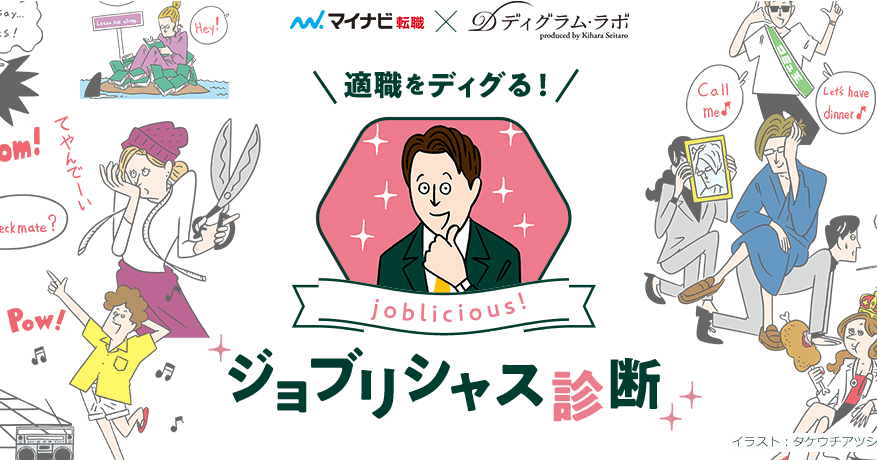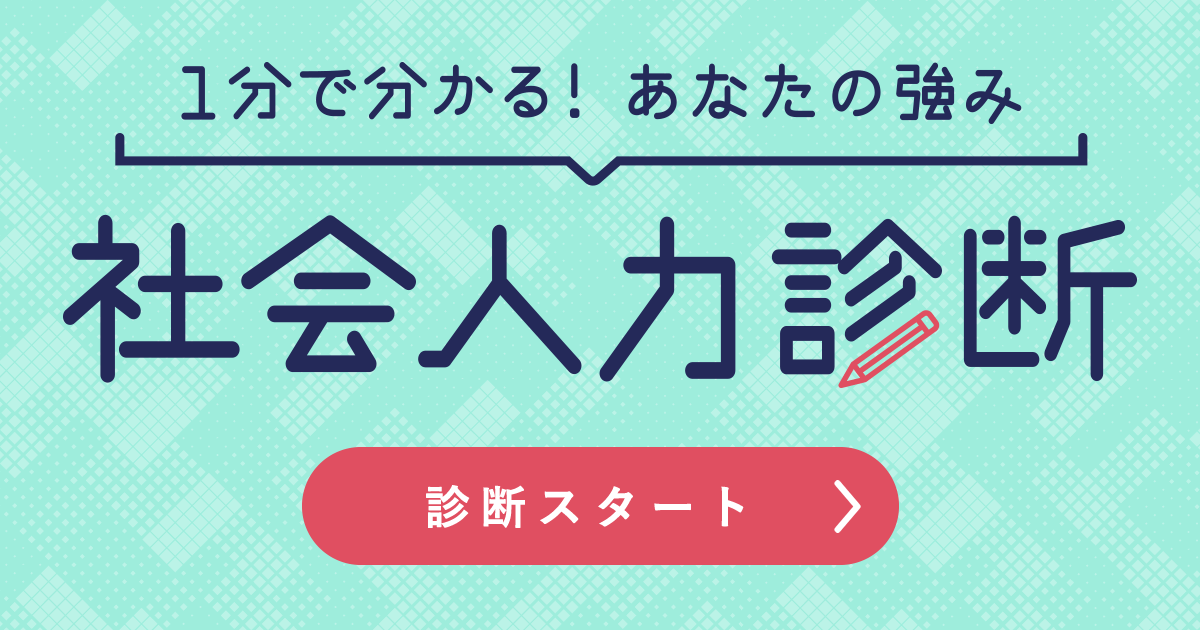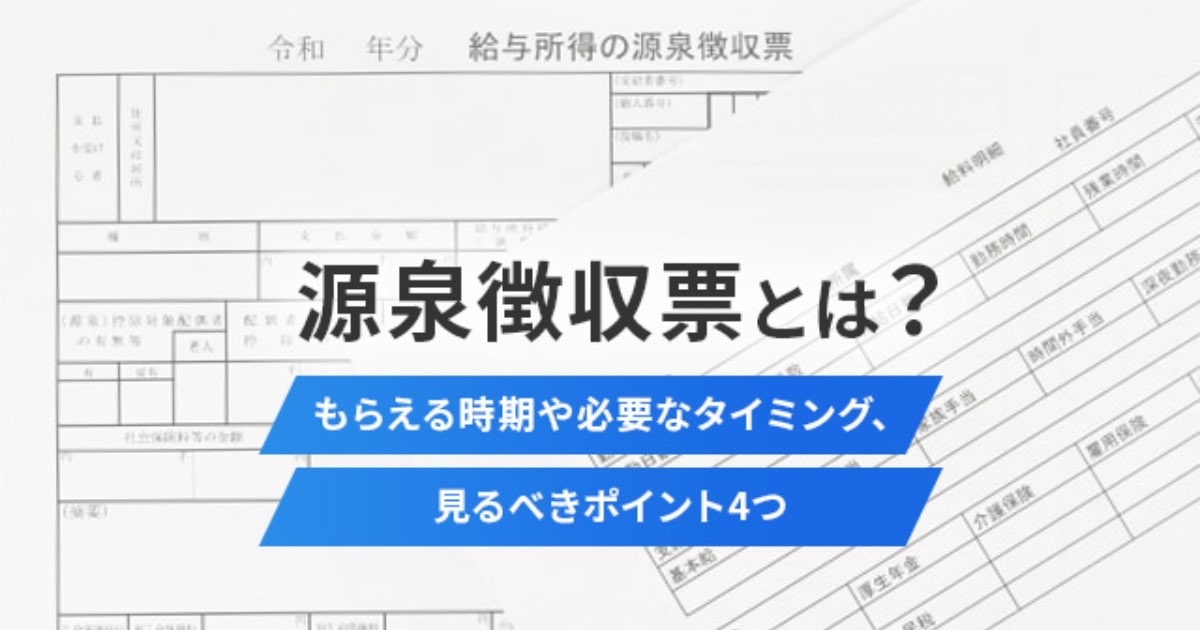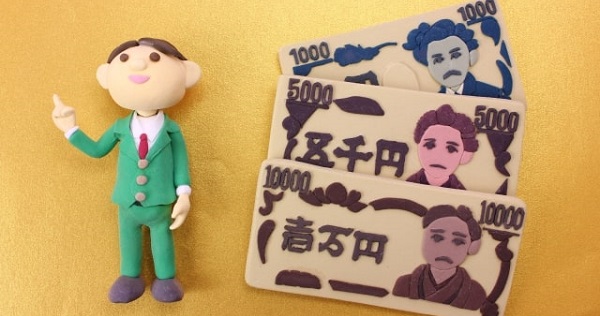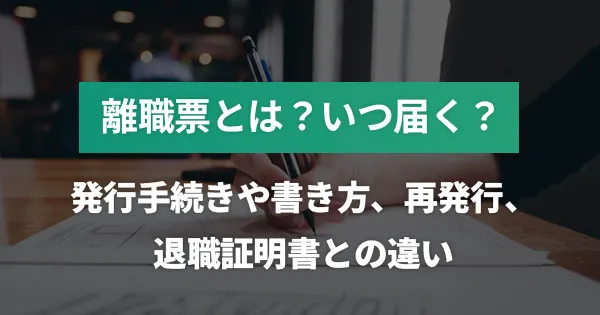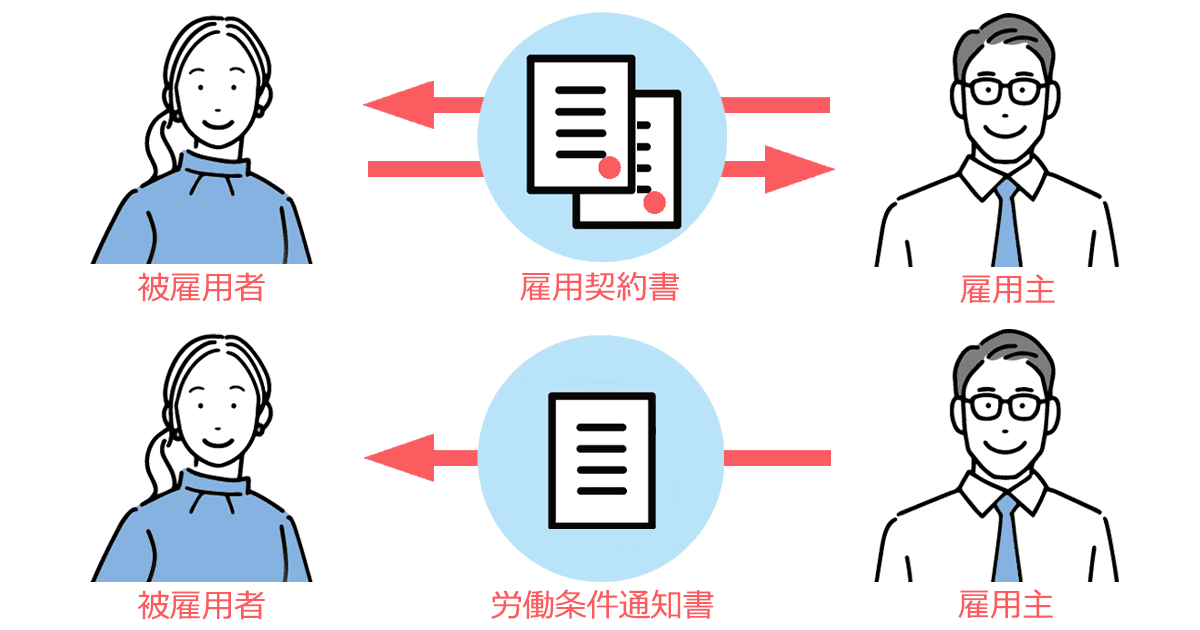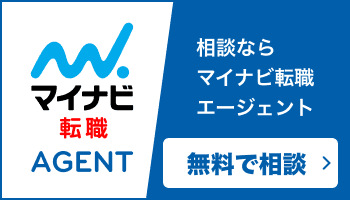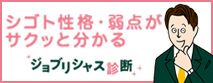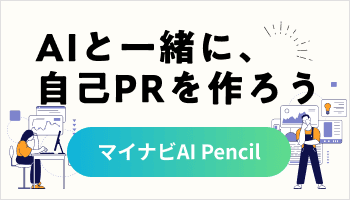60秒ビジネスハック
コーチングとは? ビジネスシーンでの必要性や基本の考え方を解説
更新日:2023.09.01
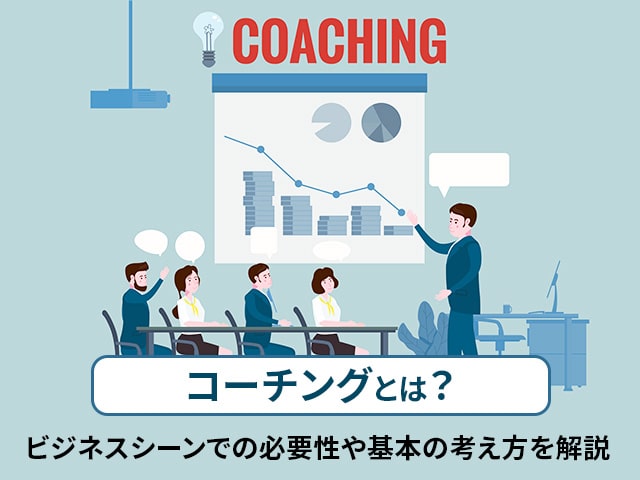
ビジネスにおける「コーチング」とは、問い掛けや対話を通して、受け手側の主体性や自発性を高める育成手法です。
後輩や部下の指導、人材育成のために取り入れたいと考えている人もいるのではないでしょうか?
そこでコーチングの概要をはじめ、基本的な考え方、カウンセリング・セラピーなどの類語との違いについて解説します。また、コーチングを取り入れるメリットと注意点も紹介しますので、理解を深めたうえでコーチングの導入を検討してみてください。
INDEX
コーチングとは?
コーチングとは、相手への問い掛けや対話を通じて、内面にある考えや新たな視点を引き出す手法です。従来の一方的に教えるスタイルではなく、「質問や対話」など双方のコミュニケーションを重要視します。
現在では、コーチングを受けた相手の「主体性」や「自発性」が高められると注目されており、多くの企業が人材育成の場面に取り入れています。
コーチングの歴史
コーチングの始まりは、1950年代。当時アメリカ合衆国のハーバード大学助教授であったマイルズ・メイス氏が、著書『The Growth and Development of Executives』で「マネジメントにはコーチングが重要なスキルだ」と記述したことから、注目されるようになりました。
更に、1980年ごろに米国企業の給与体制が個人ごとの能力や成果に対する報酬の傾向に変わり、管理職が部下のパフォーマンスを高める必要性が出てきたこともあり、アメリカ国内でコーチングが広まっていきました。
日本では、1990年代から広く浸透しはじめ、ビジネス分野のほか、医療従事者が患者に対するコーチングや、教師が生徒に対するコーチングなどあらゆる分野で広まり、コーチングの啓蒙(けいもう)に努める法人設立も多く見られています。
太平洋戦争当時、連合艦隊司令長官を務めた山本五十六(やまもと いそろく)が残した「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」という有名な言葉があります。多くの経営者や指導者が心にとどめたこの格言には、人材育成におけるコーチングのポイントが凝縮されており、現代のビジネスシーンにも生かされています。
コーチングの基本の考え方
コーチングの三原則は以下のとおりです。
- 「インタラクティブ(双方向)」
双方向のコミュニケーションによって、気づきを促すこと - 「オンゴーイング(現在進行形)」
対象者と継続的に関わりを持ち、パフォーマンスを徐々に高めていくこと - 「テーラーメイド(個別対応)」
対象者の能力や特徴、思考、成果に合わせて対応方法を臨機応変に対応していくこと
コーチングを行うためには、この3原則を押さえ、すべての要素を含めることが求められます。
コーチングとよく似た用語との違い
コーチングには、似たような言葉がいくつか存在します。ここでは、カウンセリングやティーチング、コンサルティング、セラピーといった、コーチングと似た言葉とコーチングの違いについて、上司と部下の関係性に照らし合わせながら解説していきます。
コーチングとカウンセリングの違い
コーチングは、目標を達成したい人が利用するサービスであるのに対し、カウンセリングは、心の不調を整え、未来に向かうことを目的としています。
またコーチングは、企業であれば上司や先輩が行いますが、カウンセリングは心理カウンセラーや精神科医が実施するという点も大きな違いです。
コーチングとティーチングの違い
ティーチングは指示を出したり、教えたりする育成手法であるのに対し、コーチングは答えを一緒に導き出す手法であるという点に大きな違いがあります。
上司が部下から答えを引き出すための質問などを行うことは、ビジネスにおけるコーチングの特徴です。一方でティーチングでは、上司や先輩が部下に答えを与えたり、身に付けているスキルや技術を提供したりします。
コーチングとコンサルティングの違い
コーチングとコンサルティングは、「課題達成」を目的としているか否かが大きな違いと言えるでしょう。
コーチングは、受け手側が自分の強みや悩みを自覚し、成長を目指すことを重視しています。それに対しコンサルティングは、部下が抱える課題を発見し、改善へと導くことを最優先して取り組みます。
コーチングとセラピーの違い
セラピーは、現在抱えている悩みや問題を解決するために行われます。それに対し、コーチングは、目標達成に向けて相手の行動変容を促すことを目的として行われます。
コーチングではセラピーのように、受け手の過去を振り返り、さまざまな原因を探ることは基本的にありません。また、心理カウンセラーや産業カウンセラーが対応する点も大きな違いと言えるでしょう。
コーチングがビジネスシーンで必要とされる理由

コーチングは、日本だけでなくアメリカでも積極的に取り入れられている育成手法の一つです。それでは、なぜこれほどに、コーチングはビジネスシーンで重要視されているのでしょうか。
その理由の一つが、変化が著しい現代社会において「自発的に判断・行動できる人材」が求められていること。自発的に判断し、行動に移せる社員は、仕事に対する意欲が高いことから、成果につながりやすいとされています。
経済産業省が公表したデータ「未来人材ビジョン」においても、「自発性」や「向上心・探究心」「意欲・積極性」の高い人材が、多くの企業に求められていることが記載されています
参照:経済産業省「未来人材ビジョン」コーチングのメリット
コーチングを実施することでさまざまな良い効果があります。ここでは、そのメリットについて解説していきます。コーチングを導入すべきか検討している人はチェックしてみましょう。
自律性が身に付く
コーチングは、質問や対話を通して、受け手側が自ら考えられるように促します。そのため、自分が目標を達成するために「何をすべきか」「何を求められているのか」ということを、深く考えることができるようになるという効果があります。
また、頭で考えるだけでなく、目標達成に向けたロードマップを作成できるようにもなっていきます。いわゆる「アウトプット力」が身に付くことも、コーチングのメリットの一つでしょう。
更に、目標を達成するまでに必要なタスクを細分化し、優先順位を付けてやるべきことを明確化させたうえで、具体的な行動に移せるようにもなります。コーチ側も、受け手側の成長を促すために計画的に進める必要があるため、判断力や主体性、計画性を高められることもメリットと言えるでしょう。
新たな特性や強みを発見できる
コーチングでは、さまざまな視点から質問を受けるため、多くの「気づき」を得ることができるというメリットがあります。
コーチのスキルが高ければ、あらゆる問い掛けによって、受け手側の発想を広げられることも魅力です。また、本人が気づかなかった特性や強み、可能性を引き出すことにもつながります。
目標達成に近づく
コーチングは「目標を達成するため」に行われるため、より効率的にゴールに近づくことができるのも良い点だと言えるでしょう。
自分のなかに目標達成地点を設けていても、結果的には自分が得たかったものと違っていたというケースもあります。また、自分の価値観やこれまでの経験に縛られ過ぎて、視野が狭くなっていることもあるでしょう。そんな時に、コーチングによって本当にかなえたい目標を明確化させることで、それに向けたより効果的な行動ができるようになるのです。
モチベーションの維持につながる
上司や先輩から指示を受けて、言われたとおりにこなすだけでは、「仕事をやらされている」というネガティブな感情が湧いてしまい、モチベーションも低下してしまいます。
コーチングを取り入れることで、自発的に考えて行動できるようになれば、仕事を「自分の成果」だと自覚できるようになり、高いモチベーションを保てるようにもなるでしょう。
コーチングの注意点
コーチングを取り入れる前に、知っておくことがいくつかあります。ここでは、コーチングの注意点について解説していきます。コーチングの効果が半減したり、無駄な時間を費やしてしまったりしないように、しっかり確認しておきましょう。
担当者との相性に左右される
コーチングは、コーチと受け手側の相性の善しあしによって、得られる効果が変わってきます。
コーチングは、相手に興味を持ち、信頼し合うことで、より良い効果が得られます。そのため、互いに距離感があったり、違和感を持ったりしたままでコーチングに取り組んでも、受け手側の本心や可能性は引き出されにくくなるでしょう。
企業が社内の従業員同士でコーチングを実施する際には、コミュニケーションを取りやすい関係性を持ったペアを組ませることも重要です。外部のコーチを依頼する場合は、コーチの人柄や従業員との相性を判断したうえで導入を検討しましょう。
結果が出るまでに時間がかかる
コーチングは、複数回行うことで受け手側の思考や行動変容を促すものです。そのため、結果が出るまでに時間がかかるということを理解しておきましょう。
一度だけの実施で大きな効果は期待できません。コーチングを導入する際は長期的な視点で捉えるようにしましょう。
コーチングのスキルを身に付けるには?
部下や後輩のモチベーションを保ちながらパフォーマンスを高められる、コーチングスキルを身に付けたいという管理職の方は少なくないのではないでしょうか。コーチングには、傾聴・質問・承認・フィードバック・リクエストのスキルが必要です。そのため、コーチングを行う側は、これらのスキルを向上させていく必要があります。
本格的にコーチングスキルを身に付けるには、資格取得を目指すのも良い方法です。コーチングの資格には下記のようなものがあるので、確認してみてください。自分に適した団体の資格を選択し、勉強を進めながら実務経験を積むことで、効率的にスキルアップできるでしょう。
- ICF CREDENTIAL ICF認定資格
- プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ(CPCC)
- 一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ資格
- 日本コーチ連盟認定コーチ
まとめ
コーチングとは、対話や問い掛けによって相手の発見や可能性を見いだす人材育成の手法です。変化が著しく、近い未来を予測できない現代社会では、「自発的に考えて行動できる人材」が求められています。コーチングを行うことで、自ら課題や問題点に気づき、対策を講じることができるようになるので、積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
監修者プロフィール
北村 正貴
ファシリテーター
北村ファシリテーション事務所代表。対話で支援するファシリテーター。「寛容で温かさのある社会をつくる」をミッションとし、チーム活動に大切な「対話の方法」を教える研修やワークショップの企画運営をはじめ、組織開発(コーチング/ファシリテーション)のコンサルティング支援を行っています。「働くことを楽しめるチーム・組織づくり」を広めるために活動中。
関連コンテンツ
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
仕事に役立つ動画
-
【仕事に活かせる】あのTikTokerやYouTuberが人気なワケとは?
-
【脳科学で解決】仕事がデキル人の脳の使い方とは?茂木健一郎先生が解説
-
未来を変える一歩を踏み出す!他人に人生を委ねる?『決めつけコーチング』
-
【セカンドキャリアの築き方】元芸人の社長が語る夢は諦めても人生は諦めない方法!
豊富な転職・求人情報と転職ノウハウであなたの転職活動を支援する【マイナビ転職】。マイナビ転職は正社員の求人を中心に“日本最大級”常時 約8,000件以上の全国各地の豊富な求人情報をご紹介する転職・求人サイトです。毎週火・金更新であなたの希望の職種や勤務地、業種などの条件から検索することができます。職務経歴書や転職希望条件を匿名で登録するとあなたに興味を持った企業からスカウトされるサービスや、転職活動に役立つ職務経歴書サンプルや転職Q&A、会員登録をすると専門アドバイザーによる履歴書の添削、面接攻略など充実した転職支援サービスを利用できる転職サイトです。