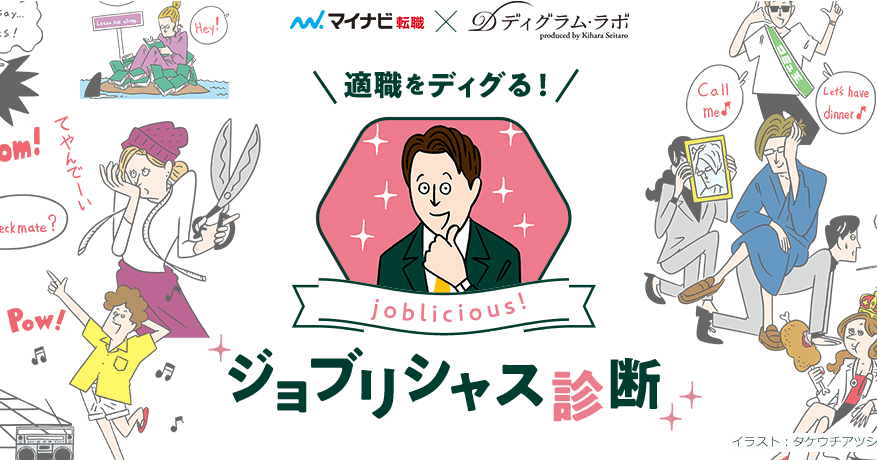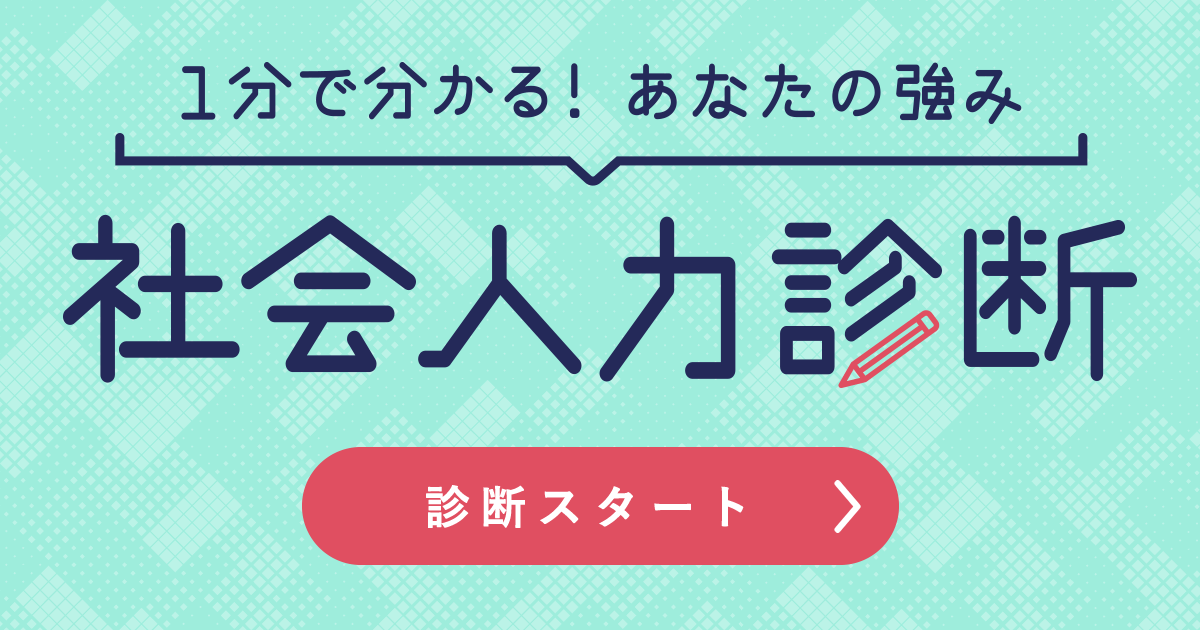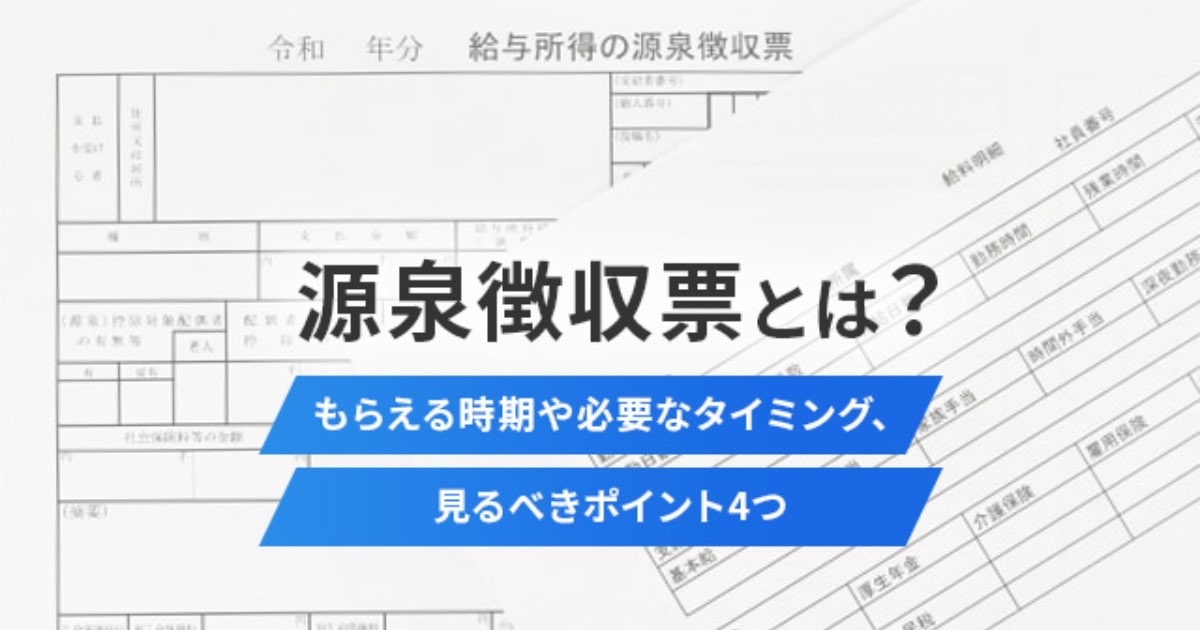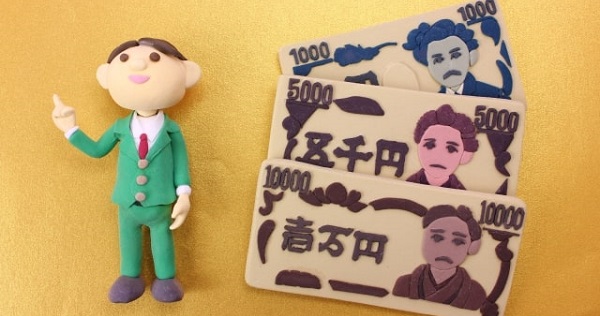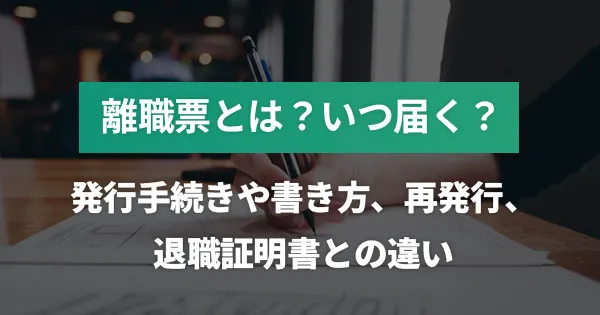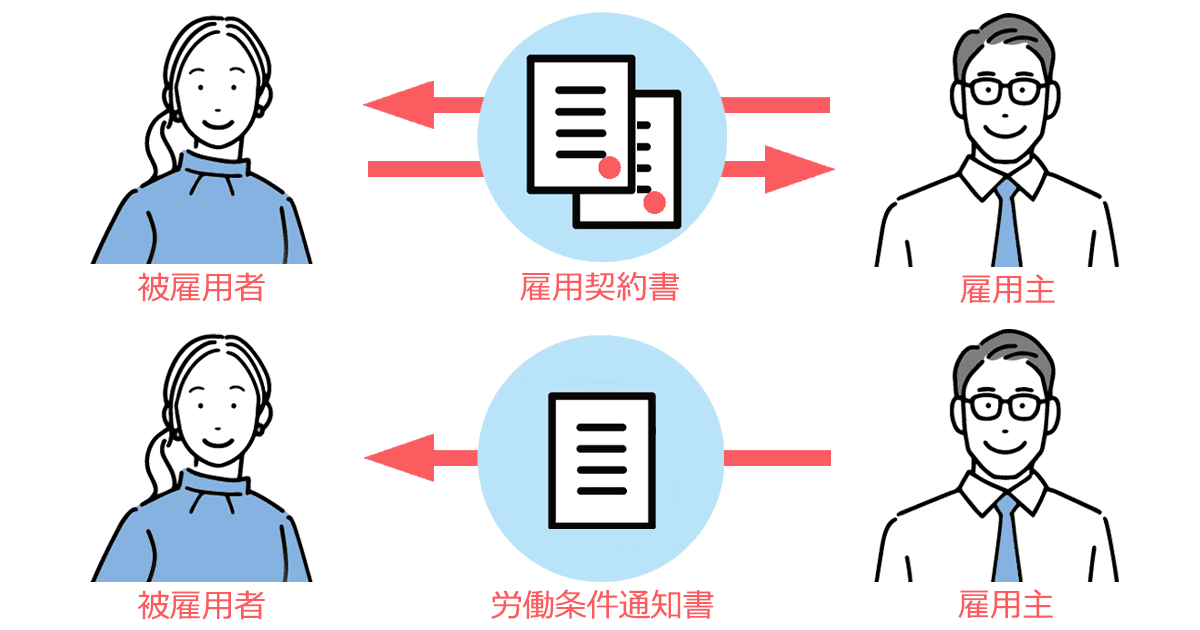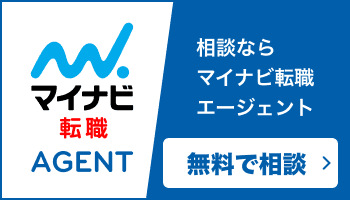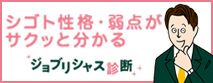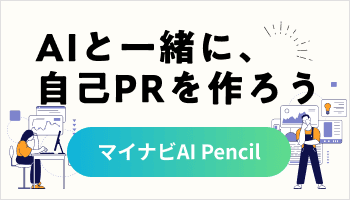ワーキングプアとは?年収の目安や日本の現状、公的支援や年収アップ方法
更新日:2024年02月02日


記事まとめ(要約)
- ワーキングプアとは、働いているものの十分な収入を得られず貧困状態にある人を指す
- ワーキングプアを定義する年収・手取り額はない
- 厚生労働省発表資料から「年収200万円以下」を目安とする見方がある
- 物価高の影響や価値観の多様化が関係している
- 就労支援や生活支援など、公的支援制度が複数ある
ワーキングプアとは、働いているものの収入が少なく、生活が困窮している人を指す言葉です。
ワーキングプアに該当する年収の目安はあるのか、ワーキングプアに該当する人の割合、また公的支援制度や収入を増やす方法などを紹介します。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
ワーキングプアとは?
ワーキングプアとは、働いているものの十分な収入を得られず貧困状態にある人を指し、「働く貧困層」とも呼ばれています。
ワーキングプアと呼ばれる人々は、より多くの収入を得るために長時間働くことで過労に至るケースも多く、健康面にも悪影響を及ぼす場合があります。
ワーキングプアの年収・手取りの目安
ワーキングプアを定義する年収・手取り額はありませんが、目安とされる基準や考え方があります。
生活保護の受給条件を基準に考える
生活保護の受給条件が一つの基準として考えられます。
なぜなら、生活保護は憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保護するための制度であり、これを下回ることは最低限度の生活が困難であると考えられるからです。
生活保護を受けるための条件はさまざまありますが、一つは収入が最低生活費より低いという場合が挙げられます。
最低生活費は厚生労働大臣が定めており、居住地、年齢、世帯の人数などにより異なりますが、東京都内で一人暮らしをしている場合では、13~14万円ほどといわれています。
年収200万円以下を一つの目安とするケースも
また、厚生労働省が発表した「非正規労働者データ資料(修正)」では年収192万円未満の人々を「一般的にワーキングプアに含まれる者」としていることから、「年収200万円」(月給約17万円、手取りにすると13~14万円)以下を目安として考えるケースもあります。
日本におけるワーキングプアの現状
日本におけるワーキングプアの現状について、国税庁が公布している資料を基に確認してみました。
令和4年、1年を通じて勤務した給与所得者は5,078万人とされています。そのうち、前述の年間給与200万円以下に該当する人の数は以下。
| 年間給与区分 | 給与所得者数 | 全体における割合 |
|---|---|---|
| 全体 | 5,078万人 | - |
| 100万円以下 | 398万5,000人 | 7.8% |
| 100万円超 200万円以下 | 643万3,000人 | 12.7% |
出典:国税庁長官官房企画課|令和4年分 民間給与実態統計調査
年収200万円以下がワーキングプアに該当すると考えると、100万円以下(7.8%)、100万円超200万円以下(12.7%)の人の割合から、1年を通じて勤務した給与所得者のうち約20%、つまり5人に1人はワーキングプアとなる計算です。
男性より女性のほうが多い
先述の調査では、年収200万円以下に該当するのは男性よりも女性のほうが多い結果となっています。
男性
| 年間給与区分 | 給与所得者数 | 全体における割合 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 98万2,000人 | 3.4% |
| 100万円超 200万円以下 | 181万8,000人 | 6.2% |
女性
| 年間給与区分 | 給与所得者数 | 全体における割合 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 300万3,000人 | 14.0% |
| 100万円超 200万円以下 | 461万5,000人 | 21.5% |
出典:国税庁長官官房企画課|令和4年分 民間給与実態統計調査
表のとおり、1年を通じて勤務した給与所得者のうち、男性の合計が280万人であるのに対し、女性は761万8,000人と3倍近い数字となっています。
理由として、男性よりも女性のほうが非正規雇用で働く人が多いことや、男女間での賃金格差があること、更に出産や育児といったライフイベントの存在が挙げられます。
中高年のワーキングプアが深刻化
近年の傾向の一つとして、中高年のワーキングプアが深刻化している現状があります。
その背景として挙げられるのは、バブル崩壊後の1990年代から2000年代、いわゆる就職氷河期といわれる時代の影響です。
正社員での就職がかなわず非正規社員などの労働形態で働き続けた結果、待遇に恵まれず、中高年になってからワーキングプアになってしまう人が少なからずいます。
非正規社員のまま年齢を重ねてしまうと正社員として採用されることが困難になっていく現状もあり、ワーキングプアが深刻化の一途をたどってしまうのです。
高学歴でもワーキングプアになることがある
一方、高学歴の人でもワーキングプアになる場合があります。
文部科学省が公表している資料によると、修士課程修了者の就職率は76.1%、博士課程修了者の就職率は69.3%となっています。
この数字から、大学院を卒業するほどの知識や学力を持ちながら就職がかなわず、非正規雇用や無職になる人が一定数いることが読み取れます。
理由としては、理想とする就職先のハードルを高く設定し就職活動がうまくいかなかったケースや、博士号を持っている人の場合は研究者という限られた枠を優秀な学生同士で競争することなどが挙げられます。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
ワーキングプアが増えた原因
ワーキングプアが増えた原因には、企業側・個人側双方の状況や考え方の変化があります。
非正規雇用が増えた
ワーキングプアが増えた原因の一つ目は、正社員ではなく非正規での雇用が拡大していることです。
現在、日本の雇用者の3人に1人が非正規雇用で働いています。働き方や時間の融通が利く非正規雇用を自ら希望する人が増えたことも事実ですが、これは企業側に非正規雇用のニーズがあるからこその結果だと考えられます。
正社員に比べて非正規の社員は給与が低く、ボーナスの支給もないことが多いです。そのため非正規雇用は正規雇用である正社員と比べてワーキングプアになる可能性が高くなります。
非正規雇用のニーズが増えた要因の一つ
90年代後半以降、グローバル化とIT化により、日本を含む多くの国の企業が安価に労働力を確保できる東南アジアなどに生産拠点を移し、自国内の拠点を縮小する方針を取りました。国際的にコスト意識が高まり、なかでも人件費を抑制する動きが活発化した結果、非正規での雇用ニーズが高まったのです。
介護や子育ての負担
原因の2つ目は、介護や子育てに時間や体力を使う必要があることです。
介護や子育てをしている場合、仕事の時間を短くする、自宅から通いやすい職場にするなど、働き方を制限する必要があります。
また、状況によってはやむなく早退や欠勤をすることにもなり、満足のいく給与が得られず、ワーキングプアになってしまう可能性があります。
物価高が影響している
原因の3つ目は、物価高の影響です。物価高は、雇用する側にもされる側にも影響を与えます。
企業にとっては、材料の値段が高くなり調達費がかさむためほかの領域でコストカットを行うなどの必要があり、給与が上がらない状況を生んでいます。
労働者にとっては、生活に必要な物の金額が上がっているのに給与は上がらないため、十分に使えるお金が少なくなってしまい、生活を大きく見直さなければワーキングプアになってしまいます。
価値観が多様化している
原因の4つ目は、働くことに対する価値観の多様化です。従来の日本では正社員として入社して定年まで働くことがスタンダードな考え方でした。
しかし近年は、仕事だけではなくプライベートに重きを置いて理想とする暮らしを実現したい、働き方や労働時間に柔軟性を求めたいなど、さまざまな志向の人がいます。
つまり、自分の意思で収入の少ない非正規雇用などを選択することで、ワーキングプアになっているケースもあるのです。
公的支援制度を利用してワーキングプアを抜け出す
就労支援や生活支援など、公的な支援制度を利用することでワーキングプアを抜け出せる可能性があります。それぞれの内容を詳しく解説します。
公共職業訓練(ハロートレーニング)
ハロートレーニングとは、希望する仕事に就くために必要なスキルや知識の習得を目指す公的な支援を指します。
全国のハローワークで受講を受け付けており、該当する人に向けた施策が用意されています。
求職者(失業者)の受講料は教材費等を除いて原則無料となっています。
- 離職者訓練、求職者支援訓練
- 在職者訓練
- 学卒者訓練
- 障害者訓練
訓練内容は、基礎的な技能を身に付けるものから実践的技能を学ぶコースまでさまざまです。その人に応じたプランでサポートを受けられます。
参照:厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」
求職者支援制度
求職者支援制度とは、再就職・転職・スキルアップを目指す人を対象に、無料の職業訓練・就職サポートを受けながら月10万円の給付金が受給できる公的支援制度です。
以下4点の要件を満たす人が該当します。受講料はテキスト代を除いて原則無料です。
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 原則、雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
主な訓練内容は以下の表をご覧ください。
| 基礎 | ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など |
|---|---|
| IT | Webアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など |
| 営業・販売・事務 | OA経理事務科、営業販売科など |
| 医療事務 | 医療・介護事務科、調剤事務科など |
| 介護福祉 | 介護職員初任者研修科、介護職員実務者研修科など |
| デザイン | 広告・DTPクリエーター科、Webデザイナー科など |
| その他 | 3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など |
職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金とは、ハロートレーニングを利用し就職を目指すなかで雇用保険を受給できない場合に、支給要件に該当すれば給付金を受給できる制度です。
以下、8つの要件をすべて満たしていれば受給できる可能性があります。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- すべての訓練実施日に出席している
- 世帯の中に給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けたことがない
全国のハローワークが窓口となっており、職業訓練を受けながら給付金が受給できる制度です。
ひとり親世帯向け支援
ひとり親世帯に向けたさまざまな支援を行う公的な制度です。
ひとり親の就業のための支援、資格取得、子どもの生活・学習支援など、幅広い支援体制があります。
また、生活・就労が困難な女性に向けた、社会との接点を保ち続けるための支援策も幅広く用意されています。
生活保護制度
生活が困窮している人に対して必要な保護を行う支援制度です。
生活必需品、家賃、子どもの学用品費、医療・介護・出産費用、就労に必要な技能習得の費用、葬祭費用など、さまざまな項目に対し扶助が支給されます。
福祉事務所または町村役場で申請の手続きが可能です。最低限度の生活を保護し、自立を促進する制度です。
税金の猶予申請
税金の納付を猶予できる制度もあります。
廃業・休業・失業、もしくは今年の所得が昨年分の所得より明らかに少なくなった場合などに申請が可能で、受領されると支払う予定の税金納付の猶予ができます。
申請方法は、e-Taxソフトで申請書を作成し提出、もしくは納税地を管掌している税務署長宛てに持参または送付で提出するといった方法があります。
年収アップなどでワーキングプアを抜け出す
ここでは、収入を増やすなどワーキングプアから抜け出すための方法についてご紹介します。
自己分析の結果をもとに転職を検討する
転職して働く場所を変えることはワーキングプアを抜け出す方法の一つですが、そのためにはまず自己分析を行いましょう。
自己分析を行うことで、あなたの強み、苦手なこと、将来仕事を通じてどうなりたいのかなどを明確にできます。
転職活動の際の企業選びの軸になりますし、面接官に対して自信を持って自分をアピールする材料にもなるでしょう。
目先の収入のことだけでなく、将来のキャリアも踏まえて、自己分析の結果をもとに自分に合う転職先を見つけることが大切です。
自己分析の方法や書き方については以下をご覧ください。
正社員として働く
給与を安定させるために正社員として働くのは、有効な方法の一つです。
非正規雇用の場合、時給制で休日の日数によって収入が増減する場合が多いですが、正社員になればほとんどの場合、月給制で働くことができ、毎月の収入を安定させることができます。
ボーナスの支給があったり、昇給の機会も正社員のほうが多いため、収入を増やしていくことも目指せます。
また、企業によっては福利厚生で子ども手当、家賃補助などが付与されることもあり、生活面の余裕につながるでしょう。
正社員の働き方についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
仕事に生かせる資格・スキルを取得する
資格を取得したりスキルを身に付けたりすることも、収入を増やす方法の一つです。
資格やスキルがあることで応募できる求人の数が増え、選考で評価につながる可能性があるからです。
これまで応募できなかった条件の良い仕事にも挑戦できるかもしれません。今の時代、ほとんどがパソコンを使った仕事であるため、Excel、Word、PowerPointといった仕事で活用されることの多いソフトの基本操作を習得することも有効です。
就職・転職に役立つ資格については以下のページでも詳しくご紹介しています。
副業を始める
副業を始めて収入を増やすのも良いでしょう。
本業の収入だけに頼らず、空き時間をうまく活用することでプラスの収入を得ることができます。
ただし、本業に支障をきたさないように注意しましょう。
また、副業を始める際には、働きすぎて健康面に悪影響を及ぼす結果にならないよう、本業とうまくバランスを取るように心掛ける必要もあります。
副業を始める際の注意点については、以下の記事も参考にしてみてください。
ワーク・ライフバランスを考える
ワーク・ライフバランスを見直すことも、ワーキングプアから抜け出す一歩になるかもしれません。
なぜなら、ワーキングプアは、ただ収入が少ないという理由だけでなく、労働時間の長さや職場環境の悪さなどとも密接に関係しているからです。
ワーク・ライフバランスを実現すれば生活の質が向上され、仕事に対するやりがいも生まれるなど、ワーキングプアから抜け出すきっかけになるでしょう。
お金の使い方を見直す
お金の使い方を見直すことも大事です。
例えば、保険料、携帯料金、インターネット代、水道光熱費など、日々の生活費で抑えられる出費はないか確認してみることで、手元に残るお金を増やせる可能性があります。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
まとめ
ワーキングプアといっても、働く意思があるにもかかわらず生活に困窮しているケースから、働き方や労働時間に柔軟性を求めて収入の少ない仕事を選んでいるケースなどさまざまです。
ワーキングプアから抜け出すことを考えているならば、ここで紹介した公的支援制度の利用や、収入を増やすため働き方を変えることなども検討してみてください。
監修者

岡 佳伸(おか よしのぶ)
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活動。各種講演会で講師を務めるほか、日本経済新聞、読売新聞、女性セブンなどへの取材記事掲載、NHK総合テレビ「あさイチ」スタジオ出演などで活躍。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
マイナビ転職 編集部
併せてチェック
豊富な転職・求人情報と転職ノウハウであなたの転職活動を支援する【マイナビ転職】。マイナビ転職は正社員の求人を中心に“日本最大級”常時 約8,000件以上の全国各地の豊富な求人情報をご紹介する転職・求人サイトです。毎週火・金更新であなたの希望の職種や勤務地、業種などの条件から検索することができます。職務経歴書や転職希望条件を匿名で登録するとあなたに興味を持った企業からスカウトされるサービスや、転職活動に役立つ職務経歴書サンプルや転職Q&A、会員登録をすると専門アドバイザーによる履歴書の添削、面接攻略など充実した転職支援サービスを利用できる転職サイトです。