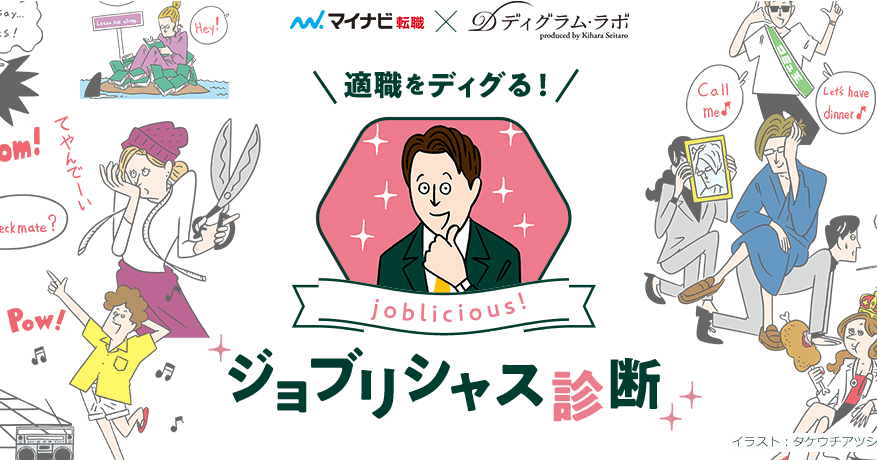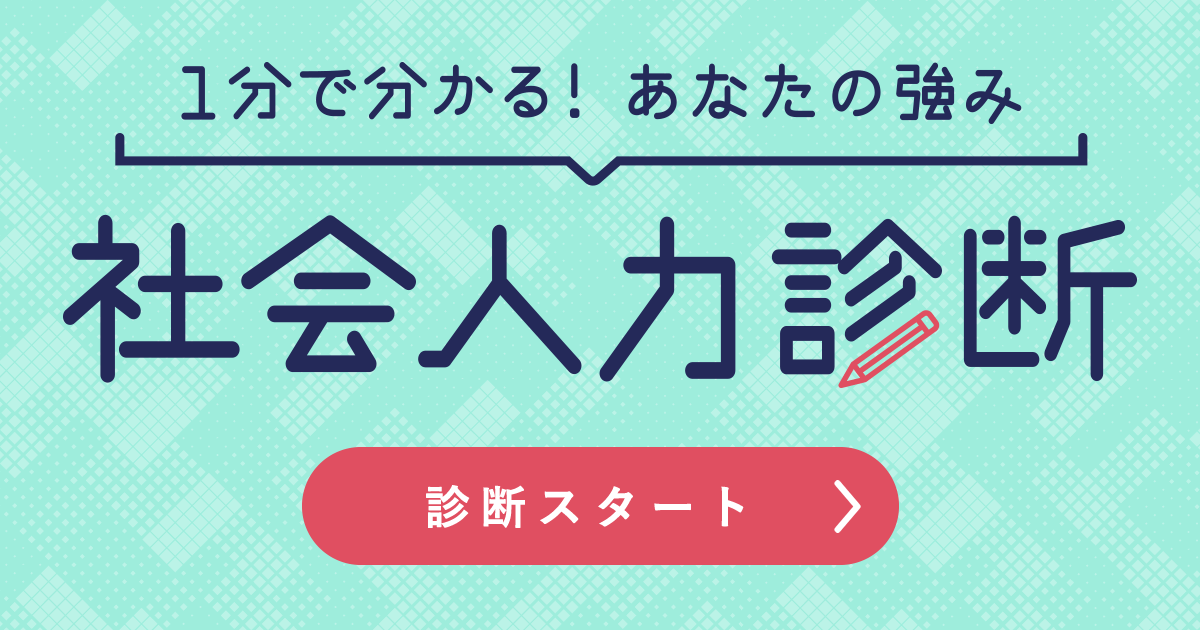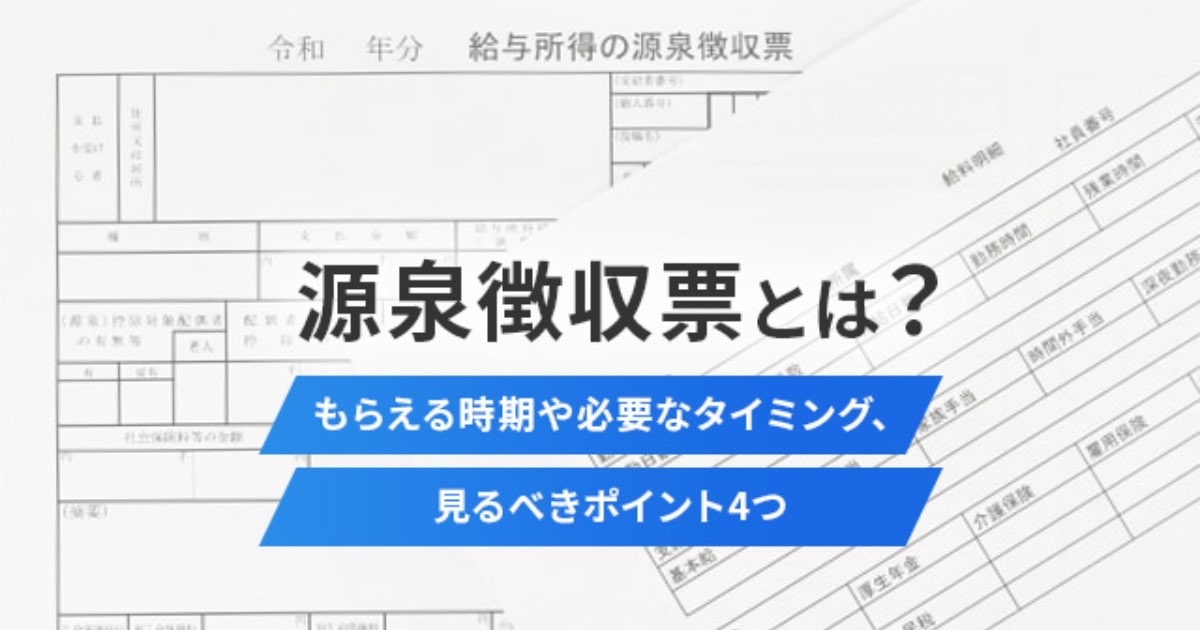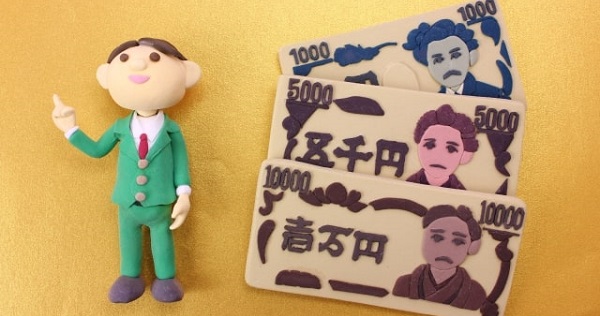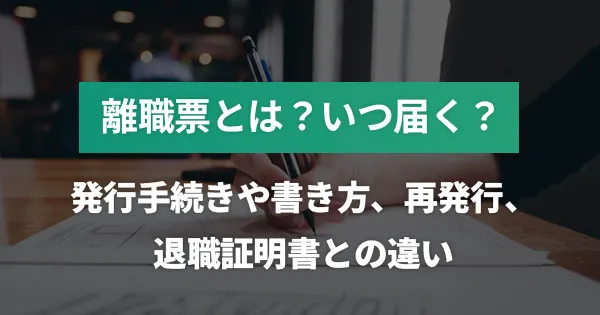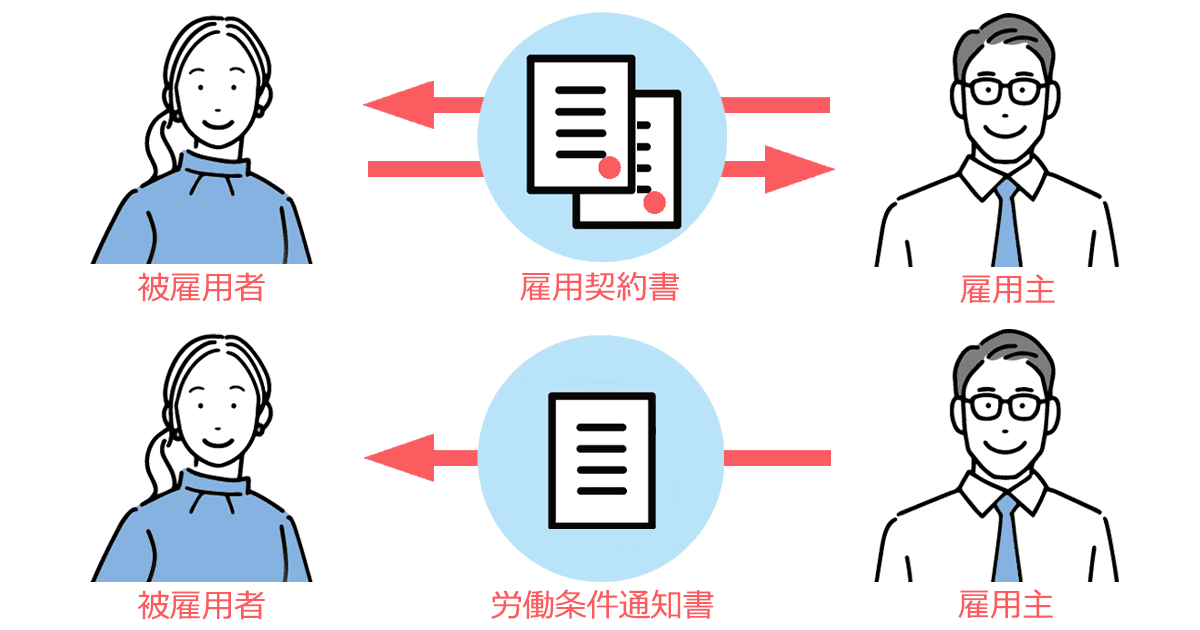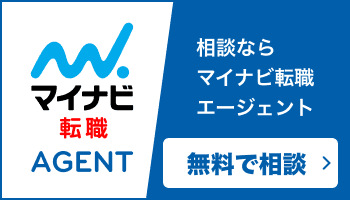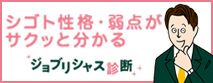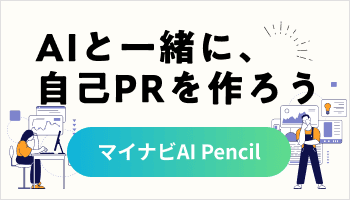時短勤務(短時間勤務制度)とは?いつまで適用される?メリットを解説
更新日:2025年07月16日


記事まとめ(要約)
- 時短勤務(短時間勤務制度)は、育児・介護休業法によって定められた制度
- 一定の要件を満たしていれば誰でも制度を利用できる
- 利用することで、育児や介護と仕事を両立しやすくなる
- ただし、給与が減少することや業務量の調整が難しいといった注意点も
- 時短勤務を利用したい時は、勤務先へ申請が必要
- 申請方法は勤務先によって異なるため、まずは人事部に確認しよう
子育てや介護といった家庭の事情により、勤務時間を短くして働く「時短勤務」を検討している人もいるのではないでしょうか。
今回は、時短勤務を利用する時に知っておきたい、時短勤務の概要や、メリット・デメリット、利用できる期間、申請方法などについて分かりやすく解説します。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
時短勤務とは?

時短勤務(短時間勤務制度)とは、育児・介護休業法により定められた制度で、1日の所定労働時間を短縮した働き方を指します。
時短勤務は、子育てや介護などと仕事との両立をサポートする制度で、国が企業に対して、制度の導入を義務付けています。
企業の就業規則などで決められている所定労働時間は、多くの場合は8時間ですが、一定の要件を満たした従業員が申請することで、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することができます。
時短勤務の対象者

時短勤務は、「子育てをしている人」もしくは「介護をしている人」が、一定の要件を満たした時に利用できます。ここでは、それぞれのケースに分けて、利用するための要件を紹介します。
子育てをしている人
子育てをしている人が時短勤務制度を利用したい場合、以下5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 日々雇用される者(1日ごとにその都度雇用契約が結ばれる状態)でないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
(※適用除外となる労働者についてはこちらで解説します)
出典:厚生労働省「改正法の下での短時間勤務制度について①」
つまり、3歳未満の子どもを養育しており、現在の企業でフルタイム勤務をしている正規雇用者であれば、基本的に時短勤務制度の利用が可能です。
また、パートや有期雇用でも、所定労働時間が6時間超で、週に3日以上働いている場合は、時短勤務を利用できる可能性があります。
時短勤務は「子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで」が適用期間となり、子どもが3歳になった日から適用外となります。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
- 図表は「育児のための両立支援制度」の「制度の概要(イメージ)」を基に作成
上図のとおり、育児・介護休業法において「3歳から小学校就学前の子どもの養育」を理由とした時短勤務は、企業の努力義務とされているため、法的な強制力はないのが現状です。
しかし、「子どもが3歳になってもフルタイムで働くのは不安」と感じる人も多いでしょう。企業によっては、3歳から小学校就学前までの時短勤務制度を、独自に設けている場合もあるため、就業規則や勤務先に確認してみることをおすすめします。
家族を介護している人
時短勤務と聞くと「育児」をイメージする人も多いかもしれませんが、要介護状態(2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)の家族を介護している場合にも時短勤務を利用できます。
ここで指す家族には、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。
法律では、少なくとも介護を理由とした短時間勤務を2回以上利用できるように、介護される対象家族1人につき連続3年以上、労働者が短時間勤務できるように制度を設けることが義務付けられています。
回数を分けて制度を利用できるため「介護休業」とうまく組み合わせながら活用できると良いでしょう。
時短勤務の対象外となる人

以下に該当する場合は、労使協定により時短勤務の適用除外となる場合があります。
- 入社1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
なお、(3)に当てはまるという理由で時短勤務の適用除外とする場合、企業は「育児休業に関する制度に準ずる措置」や「フレックスタイム制度」「時差出勤の制度」など、時短勤務に代わって従業員の負担を軽減するための措置を設ける必要があります。
時短勤務のメリット

時短勤務の大きなメリットは、フルタイム勤務に比べ、時間にゆとりが持てることです。
育児や介護を仕事と両立しながら行うことは、体力的にも大きな負担が掛かります。また、自分の時間や家族との時間を確保しにくくなります。
時短勤務を活用することで、ワーク・ライフバランスを取りやすくなることは大きなメリットでしょう。
時短勤務のデメリット

時短勤務には、ワーク・ライフバランスが取りやすくなるメリットがある一方で「業務量の調整が難しい」「給与が減る」といったデメリットもあります。
業務量の調整が難しい
通常の就業時間よりも短い時間で仕事を終わらせるためには、業務量や業務内容の調整が必要になります。時には周囲に頼ったり相談したりすることも必要になるため、人によっては「周囲に気を使ってしまう」と感じることもあるでしょう。
時短勤務を申請する前に上司と相談し、業務量や内容を調整することが大切です。
給与が減る
時短勤務を選択することで、基本給が減ってしまうことはデメリットとして挙げられます。時短勤務の利用を開始する前に、家計の見直しをしておくと良いでしょう。
時短勤務利用時の基本給の計算方法は、こちらを確認してください。
時短勤務の雇用形態は?

正社員として働いている場合、時短勤務により就業時間が短縮されることで「雇用形態が変わるのではないか」と心配になる人もいるかもしれません。
しかし、短時間勤務制度を利用した場合でも、雇用形態は正社員のままです。安心して時短勤務の申請を行いましょう。
育児・介護以外で時短勤務できる?
育児や介護以外に「ワーク・ライフバランスを確保したい」「キャリアアップのために大学に通いながら働きたい」「定年後も働き続けたい」など、さまざまな理由で時短勤務を希望する人もいるでしょう。そのニーズに対応するために企業が導入する制度は「短時間正社員制度」と呼ばれます。
この制度を利用する場合、下記のような労働条件となります。
短時間正社員の労働条件
引用元:厚生労働省「短時間正社員」
- 雇用形態:正社員
- 労働契約:期間の定めのない労働契約
- 労働時間:フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い
- 賃金などの待遇:同種のフルタイム正社員と同一の時間賃率、賞与・退職金等の算定方法
- 社会保険:適用
近年では、副業をしながら働く人や、大学院に通いながら働く人、持病による療養から復職した人、定年後も働き続ける人など、働く人の事情も多様化しています。
フルタイム勤務が難しい人の事情に配慮し、すべての人に活躍してもらえるように、短時間正社員制度を人材確保に役立てている企業が増えています。
時短勤務を勤務先に申請する方法

時短勤務を利用するには、勤務先への申請が必要です。申請方法は勤務先によって異なりますが、一般的には下記の流れで行われることが多いです。
【例:育児を理由とした時短勤務を申請する流れ】
- 時短勤務を開始する1カ月前までに「育児短時間勤務申出書」を人事部に提出する
- 勤務先から「短時間勤務取扱通知書」をもらう
- 上司や同僚に復帰日時や復帰後の勤務時間などを伝える
まずは、勤務先の就業規則を確認し、短時間勤務制度の申請方法を確認しましょう。分からない場合は、人事部に直接確認すると良いでしょう。
その後、人事部より「育児短時間勤務申出書」を受け取り、必要事項を記載したうえで提出します。時短勤務を開始する1カ月前までに提出するのが一般的ですが、勤務先によっては2カ月前までとしている場合もあるため、併せて確認しておきましょう。
育児短時間勤務申出書を提出した後は、勤務先から「短時間勤務取扱通知書」が付与されます。通知書には、時短勤務時の労働条件も記載されているため、受け取り後しっかりと確認しておきましょう。
時短勤務中の給与はどうなる?

時短勤務の期間中は、勤務時間が短縮されますが、給与はどのように変化するのでしょうか。時短勤務中の給与事情について詳しく解説します。
1.時短勤務における基本給
時短勤務を利用する正社員の場合、同じ職種・職位のフルタイム正社員への支給額を基準に、労働時間に比例して減額したものが基本給となります。
時短勤務時の基本給は「フルタイム正社員の基本給×時短勤務時の所定労働時間÷本来の所定労働時間」で求められます。
上記の計算式をもとに、簡易的に基本給のシミュレーションをしてみましょう。シミュレーションの条件は下記のとおりです。
- 同じ職種・職位のフルタイム正社員への支給額:20万円/月
- 所定労働時間:8時間/日
- 実労働時間:時短勤務のため6時間に短縮/日
- 所定労働日数:20日
この条件の場合、時短勤務における基本給は以下のように計算されます。
20万円×(6時間×20日)÷(8時間×20日)=15万円
簡易的な計算になりますが、フルタイムの基本給と比較して約25%給与が少なくなることが予想されます。更に、子どもの病気やケガなどで欠勤する場合は、更に減額となる可能性もあるでしょう。
事前に時短勤務中の基本給をシミュレーションしておき、家計の見直しをすると良いでしょう。
2.時短勤務における残業代
「そもそも時短勤務時に残業していいの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。結論からお伝えすると、時短勤務時の残業は可能であり、残業代も発生します。
ただし、これは時短勤務制度を利用する従業員が了承している場合に限ります。従業員が「残業免除」の申請をしている場合は、企業が残業を強制することは禁止です。
なお、残業には大きく分けて「法定時間外残業」と「法定時間内残業」があり、どちらの残業に該当するかで残業代が変わります。
| 法定時間外残業 | 労働基準法で定められる法定労働時間を超過して残業すること |
|---|---|
| 法定時間内残業 | 法定労働時間(8時間・週40時間)の範囲内で残業すること |
法定時間外残業の場合、通常賃金に25%割増で残業代を支払うことが、労働基準法で定められています。
しかし、時短勤務時の原則の就業時間は6時間であり、8時間労働までは法定時間内の扱いとなるため、この場合は残業代の割増はされません。
上記を踏まえると、時短勤務時における残業代の計算方法は下記のようになります。
| 法定時間外 残業の残業代 |
通常の1時間当たりの賃金×残業時間×1.25 |
|---|---|
| 法定時間内 残業の残業代 |
通常の1時間当たりの賃金×残業時間 |
とはいえ、そもそも「時短勤務」は、仕事と家庭を両立するための制度であるため、頻繁に残業をするのはあまり望ましいことではないでしょう。時短勤務を利用しているが、業務量が多く残業が続いているといった場合は、残業免除の申請も検討しましょう。勤務先の就業規則を確認したうえで人事部に相談すると良いでしょう。
3.時短勤務における賞与(ボーナス)
時短勤務時の賞与(ボーナス)は、フルタイム正社員と同様の基準で支給することが原則とされています。賞与の支給基準のベースが基本給の場合は、基本給が労働時間に比例して減額されるため、給与と同様に短縮した分だけ減額されるケースが多いです。
ただし、賞与の支給は労働基準法に定めがなく、企業側に金額の決定権が委ねられています。時短勤務中の賞与が気になる場合は、就業規則の確認や、人事部に確認してみることをおすすめします。
時短勤務に関するよくある質問

時短勤務に関するよくある質問を紹介します。
転職してすぐに時短勤務はできる?
時短勤務の適用除外要件の一つとして「入社から1年が経過していること」があります。そのため、労使協定を締結している企業の場合、入社1年未満の社員は時短勤務の適用除外となる可能性があります。
1年以内に時短勤務を利用したいと考えている場合は、転職は控えたほうが良いでしょう。
1時間だけ時短勤務はできる?
時短勤務による1日の所定労働時間は原則6時間ですが、短縮できる時間は企業の判断によります。例えば、所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務などにより所定労働時間を短縮する措置をあわせて設けることも可能です。
短縮できる時間の単位や、どのような措置が取られているかは企業によって異なるため、就業規則を確認したり、人事部に相談したりすることをおすすめします。
子どもが小学校を卒業するまで時短勤務できる?
育児を目的とした時短勤務の場合、適用期間は「子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで」となっています。
3歳以降も時短勤務を適用するかどうかは、あくまで企業側の「努力義務」になるため、小学校卒業まで時短勤務ができるかは企業によって異なります。
参考までに、厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」によると、短時間勤務制度を実施している事業所のうち、時短勤務の最長利用期間は「3歳未満」が最も多く38.1%を占める結果となりました。
| 3歳未満 | 38.1% |
|---|---|
| 3歳~小学校就学前の 一定の年齢 |
6.1% |
| 小学校就学の始期に 達するまで |
19.8% |
| 小学校入学~ 小学校3年生(または9歳) |
6.6% |
| 小学校4年生~ 小学校卒業(または12歳) |
6.5% |
| 小学校卒業以降まで | 23.0% |
出典:厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」
- 「表3 育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合」を基に作成
なお、「小学校就学の始期まで」が19.8%、「小学校入学〜3年生まで」が6.6%、「小学校4年生〜卒業まで」が6.5%となっており、「小学校就学から卒業まで」時短勤務の利用ができる事業所は全体の1割程度となっていました。
現状は「3歳未満」を最長利用期間にしている事業所が多いことが分かります。「小学校卒業まで時短勤務を希望したい」といった場合は、まずは勤務先の就業規則を確認したうえで、上司や人事部に相談できると良いでしょう。
時短勤務の給付金はいつから?
2024年4月現在、政府は少子化対策の一環として「時短勤務の活用を促すための給付」の創設を表明しています。具体的には、2歳未満の子どもを養育しながら時短勤務をしている人を対象に、賃金の1割相当を給付金として支給する制度です。
時短勤務を選択することで給与の減少は避けられませんが、給付により負担軽減につながる可能性は大いにあるでしょう。
給付金制度は、2025年度からの実施が予定されており、現在は具体的な制度の検討が進められています。
まとめ:時短勤務を利用して家庭と仕事を両立させよう

育児や介護に携わる人にとって、時短勤務の利用はワーク・ライフバランスを実現する方法の一つです。国は、育児と仕事の両立を促す目的で、時短勤務に関する支援を多く実施しており、期間を定めずに時短勤務ができる制度を導入する企業も増えつつあります。
制度を利用することで、家庭と仕事の両立がしやすくなります。ワーク・ライフバランスを維持するためにも利用を検討してみましょう。
監修者

塚本 泰久
社会保険労務士
ツカモト労務管理事務所 代表
関西地区を中心に、地域に密着した親切丁寧な事務所を目指しています。会計事務所での経験から、企業の労務管理と財務状況とのバランスを重視した適切なアドバイスを行うことで、より良い企業の体制作りをサポートしています。
マイナビ転職 編集部
≪こちらもチェック!≫
豊富な転職・求人情報と転職ノウハウであなたの転職活動を支援する【マイナビ転職】。マイナビ転職は正社員の求人を中心に“日本最大級”常時 約8,000件以上の全国各地の豊富な求人情報をご紹介する転職・求人サイトです。毎週火・金更新であなたの希望の職種や勤務地、業種などの条件から検索することができます。職務経歴書や転職希望条件を匿名で登録するとあなたに興味を持った企業からスカウトされるサービスや、転職活動に役立つ職務経歴書サンプルや転職Q&A、会員登録をすると専門アドバイザーによる履歴書の添削、面接攻略など充実した転職支援サービスを利用できる転職サイトです。