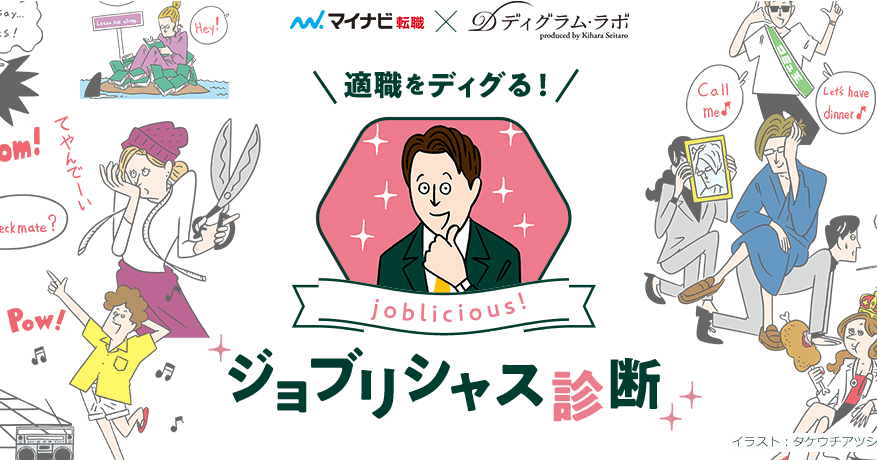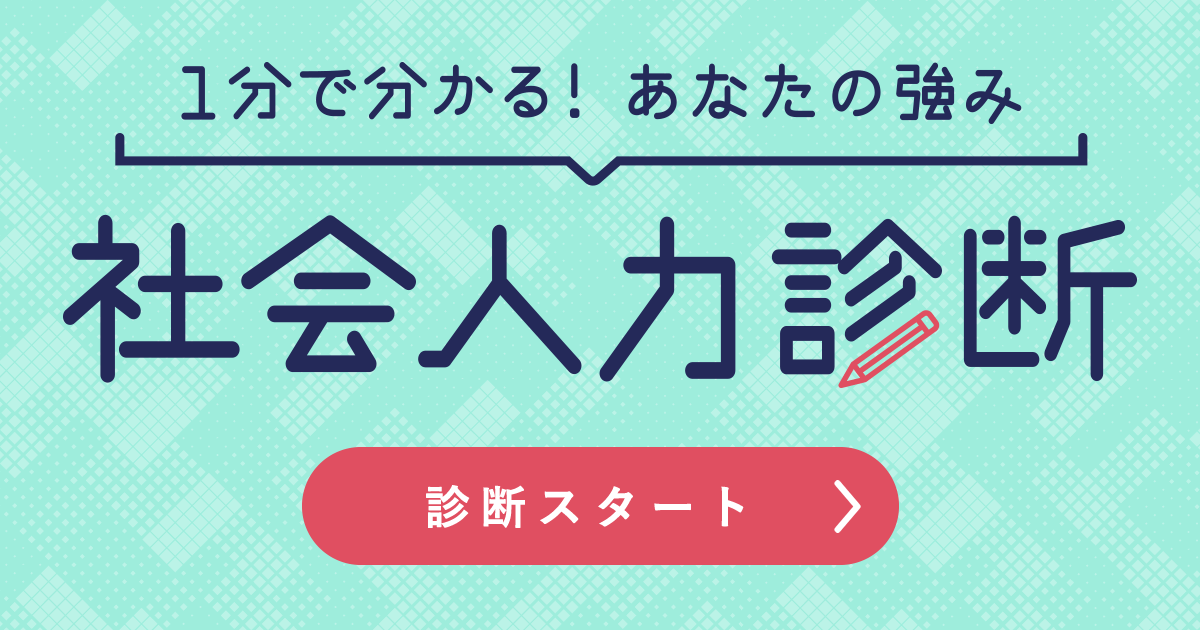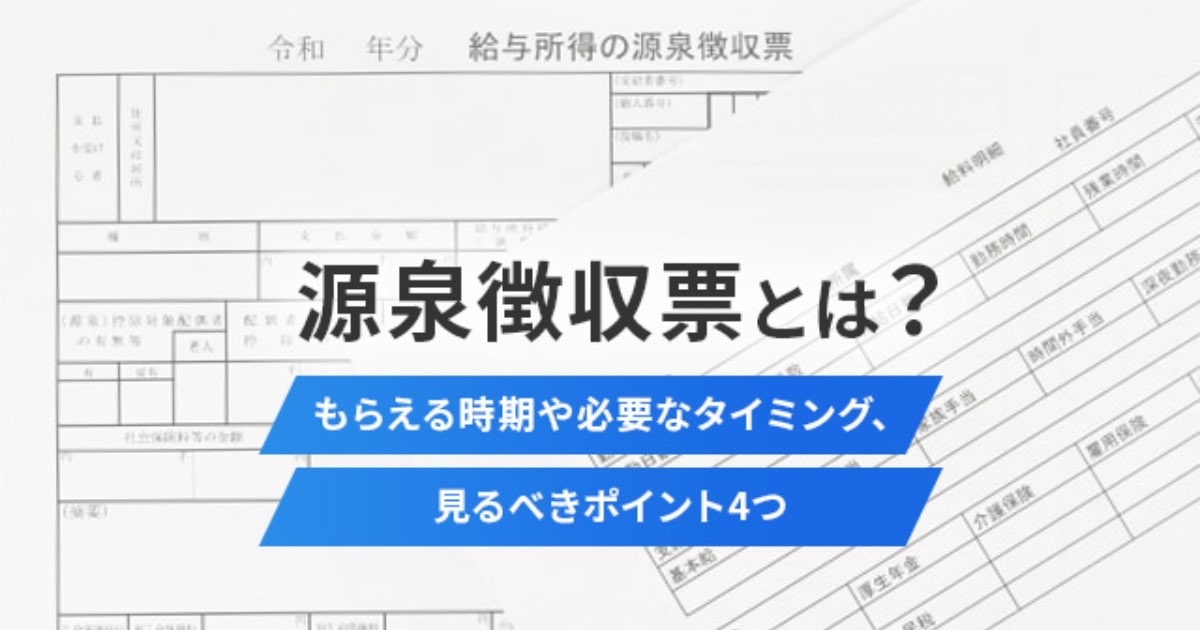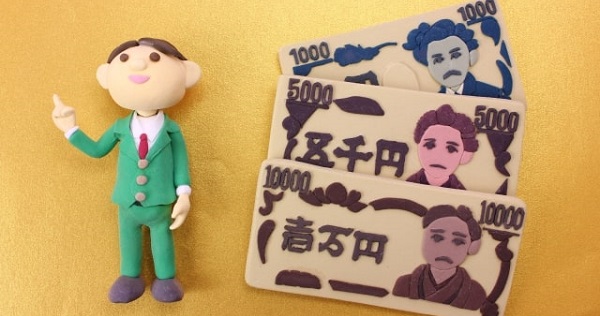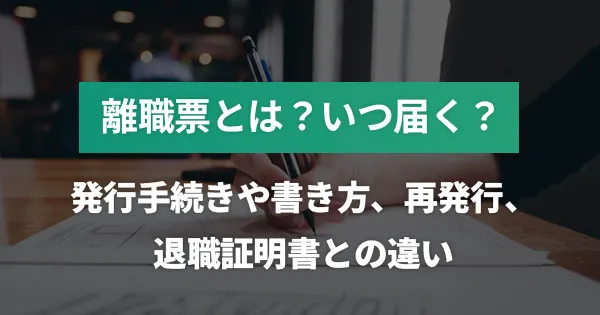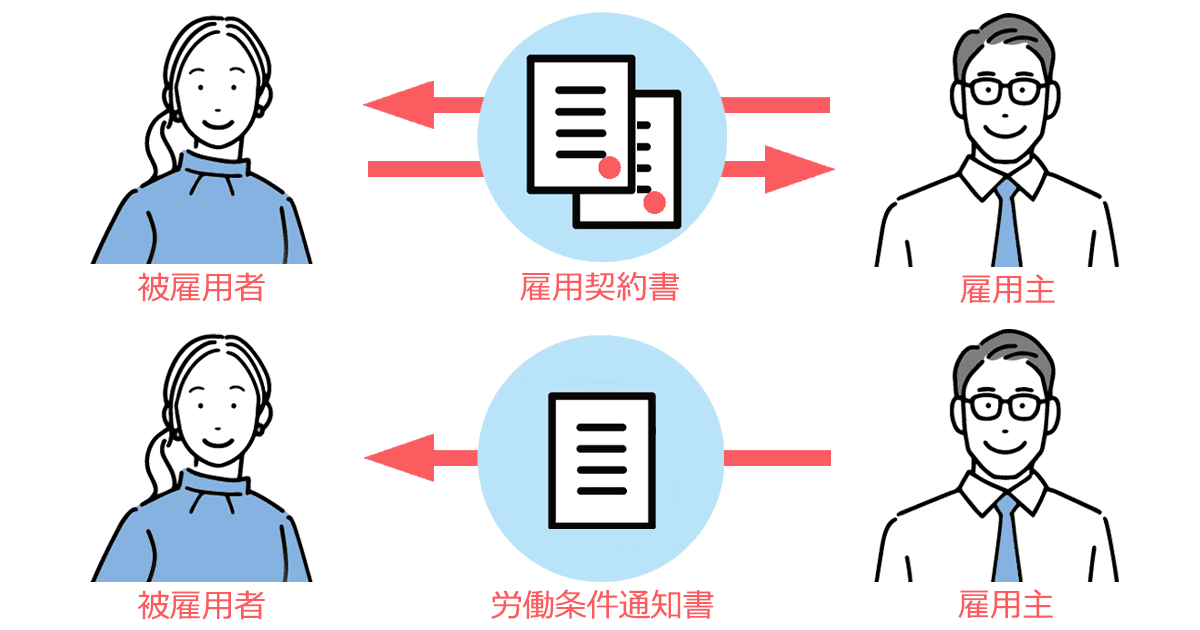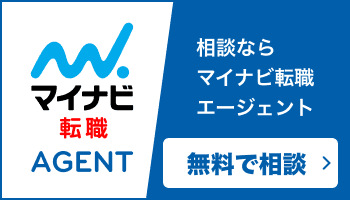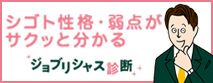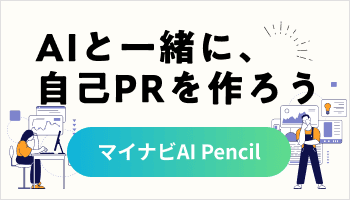保険証(医療保険)の種類や色の違いは?それぞれの特徴やマイナ保険証での確認方法
更新日:2026年02月06日
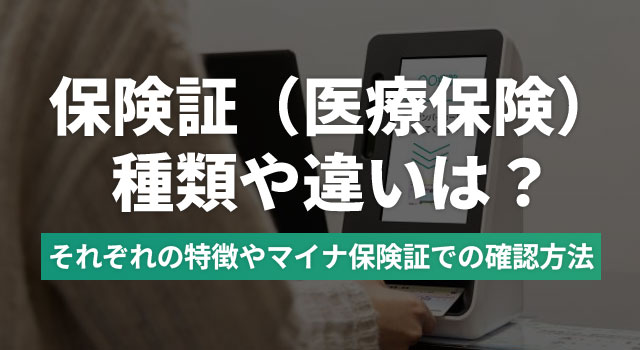

監修者篠田 恭子
特定社会保険労務士/おひさま社会保険労務士事務所 代表
記事まとめ(要約)
- 日本の公的医療保険は「健康保険(被用者保険)」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の主に3種類
- 職業や年齢で加入先が異なる
- マイナ保険証だと切り替えの際、新たな保険証の発行はされない
- 保険ごとに保険料や保障内容が異なり、変更時の手続き方法も違う
- 保険証の種類が異なっても、医療機関での自己負担額の割合は原則平等
日本の公的医療保険は大きく「健康保険(被用者保険)」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つに分かれ、国民全員が医療を受けられる仕組みです。
転職や離職時には保険が変更されることがあり、マイナ保険証の導入で制度も一部変わりました。
必要の際に備えて、加入保険と手続きを確認しておきましょう。
公的医療制度とは
日本の公的医療制度は、すべての国民が医療保険に加入する「国民皆保険制度」を採用しています。職業や年齢に応じて主に3つの保険に分類され、更にいくつかの種類があります(すぐに詳細を知りたい方はこちら)。
健康保険(被用者保険)
- 組合健保
- 協会けんぽ
- 共済組合
国民健康保険
- 市町村国保
- 国保組合
後期高齢者医療制度
保険の種類により、負担する保険料の計算方法が違ったり、受けられる保障の内容に異なる部分があったりします。
以前は保険証の見た目で、加入している保険制度を判断することができました。しかし、マイナ保険証の導入により、マイナンバーカードを利用する場合は、見た目ですぐに加入している保険を判断することができなくなりました。
このため、ご自身の加入している制度を確認したい場合は、マイナポータルで確認します。
マイナ保険証のしくみ

マイナ保険証はマイナンバーカードを保険証として利用する制度です。ここではマイナ保険証の基本的な仕組みをご説明します。
マイナンバーカードを保険証として利用登録する方法
利用登録をすることで、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。
登録は医療機関や薬局に設置してあるカードリーダーやマイナポータル、またはセブン銀行のATMから行えます。
出典先:マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省
マイナ保険証のメリット
医療機関同士で情報共有が可能なことから、適切で迅速な診療や処方が可能になり、医療の質が向上します。
また、保険証の切り替えや高額療養費制度などの手続きが簡略化され便利になります。更に、顔認証または暗証番号による認証のため、これまでの保険証よりも不正防止の効果が大きいことが期待されます。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
保険の種類

上述したように、公的医療保険制度には大きく3つの種類がありますが、更にいくつかの種類があります。
以下では、各保険についての細かい種類や特徴について1つずつ説明します。
健康保険(被用者保険)とは
健康保険(被用者保険)とは、会社員・公務員・教職員と、その扶養家族が加入できる公的医療保険です。
保険を提供する「保険者」は会社や団体となり、企業や団体に勤めている場合には、何らかの健康保険(被用者保険)に入っています。
健康保険(被用者保険)には「組合健保」「協会けんぽ」「共済組合」の3つの種類※があり、勤め先によって異なります。
- このほか船員保険もありますが本記事では省略します。
組合健保
まず、組合健保について見ていきましょう。
組合健保の正式名称は「組合管掌健康保険」です。組合健保は、特定の企業や業界の従業員およびその家族が加入する健康保険制度です。
組合健保を利用するにあたり、企業は厚生労働大臣の認可を受けて単一あるいは複数の企業で組合を設立し、健康保険法にもとづいて運営します。
組合は、単一で設立する場合には常時700人以上の従業員がいること、複数で設立する場合には合計で常時3,000人以上の従業員がいることを設立の条件としています。
協会けんぽ
次に、協会けんぽがあります。協会けんぽの正式名称は「全国健康保険協会管掌健康保険」で、主に中小企業の従業員と、その扶養家族が加入する健康保険です。
本部と全国47都道府県に設置された支部で構成されており、地域ごとに保険料率が設定されます。
共済組合
共済組合は、主に公務員や一部の公的機関に所属する方々のために設立された健康保険制度です。
共済組合は、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の3つに分類され、運営されています。それぞれ、以下のような職種や団体に属する方々が加入します。
- 国家公務員共済組合:中央省庁や国の機関で働く国家公務員
- 地方公務員共済組合:地方自治体(市町村や都道府県など)で働く地方公務員
- 私立学校教職員共済:私立学校(小中高や大学など)の教職員
任意継続制度
任意継続被保険者制度は、本人が希望する場合、退職後も一定の条件を満たすことで、在職中の健康保険に引き続き加入できる制度です。
具体的には、退職日までに継続して2カ月以上被保険者(共済組合の場合は退職の前日まで引き続き1年以上組合員)であり、退職後20日以内に所定の手続きを行う必要があります。
この制度を利用すると、傷病手当金や出産手当金を除き、在職中と同様の保険給付を受けることが可能です。ただし、保険料は全額自己負担となり、加入期間は最長で2年間です。
国民健康保険
国民健康保険は、ほかの医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度等)に加入していない方が加入する健康保険です。
都道府県および市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されています。
日本の公的医療保険制度の一部であり、国民皆保険の制度に基づいて、被用者や後期高齢者でない場合も、すべての国民が何らかの形で医療保険に加入することが義務付けられています。
市町村国保
市町村国保は地方自治体(市町村と都道府県)が運営しています。
その地域に住む被用者保険加入者または国保組合加入者以外の方で、自営業者、フリーランス、学生など、幅広い方が対象となります。転職中で無職の期間がある場合などにも、加入対象となります。
国保組合
国保組合の正式名称は「国民健康保険組合」で、特定の業種や職種の団体がそれぞれに設立・運営しています。
医療、建設業、理容業など、特定の職業に従事する組合員および組合員の世帯に属する方が加入できます。例えば、医師国保や全国土木建築国保など業種に特化した保険があり、業界特有の健康管理や福祉サービスが提供されることが多くあります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳になるとすべての方が公的医療保険制度から移行する医療制度です。扶養家族も75歳時点で扶養から外れるため、自動的に移行されます。
都道府県単位の広域連合が運営し、「後期高齢者医療被保険者」としてマイナ保険証に登録されます。
また、一定の障がいがあり、認定を受けた65歳以上75歳未満の方も任意で加入することができます。
「一定の障がい」とは、以下のような特定の基準を満たす障がいを有している場合が該当します。
- 障害年金1級、または2級を受給している
- 身体障害者手帳(1級~3級と4級の一部)を持っている
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級を持っている
- 療育手帳の1度または2度(※)を持っている
- 自治体により基準が異なります。
上記以外でも、医療機関や自治体で認定を受けた障がいがある場合も含まれることがあります。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
保険による違い

公的医療保険制度にはさまざまな違いがあります。ここでは保険料の計算方法と受けられる保障について説明します。
保険料の計算方法
保険料は、原則的に加入者の給与や賞与などの所得に基づいて計算されます。そのほかにも、種類ごとに以下のような違いがあります。
| 保険の種類 | 保険料の計算方法 |
|---|---|
| 健康保険 (被用者用) |
|
| 国民健康保険 |
|
| 後期高齢者 医療制度 |
所得に基づく保険料、均等割と所得割がある。 |
健康保険(被用者保険)の場合、算出された保険料は、給与から天引きされる形で支払われます。
一方、国民健康保険は、自ら金融機関などで支払う必要があります。
後期高齢者医療制度の支払い方法は、年金からの天引きと、自身で納める方式の2種類があり、一定以上の公的年金を受給している方は原則として、年金から自動的に差し引かれます。
受けられる保障
どの保険であっても、医療機関における診察、治療、検査、入院など、基本的な医療サービスはカバーされます。
一方で、一部の医療サービスや保障される手当などに、以下のような違いがあります。
- 健康保険(被用者保険):傷病手当金と出産手当金という2つの保障が受けられる。
- 国民健康保険:標準的な医療サービスはカバーされるが、地域や業界によってサービスが異なる。原則、傷病手当金や出産手当金は含まれない(国保組合の独自のサービスで例外あり)。
- 後期高齢者医療制度:高齢者向けの医療サービスあり。長期的なケア、リハビリテーション、治療など、高齢者に特化したサービスが含まれる。
色による保険証の違い
マイナ保険証以前の保険証では、発行元(保険者)によって、色やデザインが異なります。
保険証の色の違い例
| 発行元 | 色 |
|---|---|
| 協会けんぽ | 水色 |
| 組合健保 | 黄色・赤・ピンクなど |
| 共済組合 | 黄色・水色など |
| 市町村国保 | 赤・ピンク・緑・灰色・紫など |
| 国保組合 | ピンク・黄・緑など |
| 後期高齢者医療制度 | エンジ色、水色や白色など |
保険証の色に意味はない
保険証の色は全国で統一した基準はなく、保険者(発行元)が決めているため、同じ保険の種類でも発行元によって色が異なることがあります。また、更新時に保険証の色が変わることもあります。カードと紙の違いも同様です。
色が違う理由としては、発行元や保険の種類を判別しやすくする目的があると考えられていますが、法令や制度で色分けが義務づけられているわけではありません。
色の違いで職業や収入がバレることはない
保険証の色だけで職業や収入の判断はできませんが、加入している組合や所属する会社名などが記載されていることがあります。
保険証の種類が異なっても、医療機関での自己負担額の割合は原則平等

保険証の種類が異なっても、医療機関での自己負担額の割合は原則平等です。自己負担割合は、被保険者の年齢や所得に応じて異なります。
後期高齢者医療制度の自己負担額は、現役世代よりも低く設定されています。
医療機関における自己負担額の割合は、以下のとおりです。
| 年齢層 | 自己負担割合(原則) |
|---|---|
| 6歳未満 | 2割負担 |
| 6歳以上70歳未満 | 3割負担 |
| 70歳~74歳 |
|
| 75歳以上 |
|
次の2つの条件を満たす場合
- 世帯内の75歳以上の方のうち、課税所得が28万円以上の方がいる。
- 「年金収入+その他の合計所得金額」が1人世帯の場合200万円以上、2人以上世帯の場合320万円以上。
保険の種類によって、詳細な適用条件や追加サービスの有無が異なる場合があります。
なお、子供の負担については一定の年齢まで無料としている市町村も増えています。対象者や条件は地域により異なるため、お住まいの自治体に確認してみると良いでしょう。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
保険を切り替えるタイミング
被保険者が保険を切り替えるタイミングは、ライフイベントや状況の変化によって訪れます。
主に、以下のようなケースが想定されます。
-
就職・転職した時
新しい職場に入った時点で、以前の職場の健康保険は失効するため、新しい職場で提供される健康保険(組合健保や協会けんぽなど)に加入します。
-
結婚していて、配偶者の扶養に入る場合
夫婦のどちらかが会社員で、配偶者がもう片方の配偶者の扶養に入る場合、現在の健康保険から配偶者の健康保険に切り替える必要があります。
-
離婚した時
離婚によって扶養から外れる場合、離婚後に自分の職場の健康保険に加入するか、国民健康保険に切り替えます。
-
75歳になった時
75歳の誕生日を迎えた日から、自動的に「後期高齢者医療制度」へ切り替わります。この切り替えは全国一律で行われ、75歳以上のすべての方が対象です。
保険の種類を切り替え・変更する方法

転職や離職、結婚や離婚などのライフステージの変化によって、保険の種類を切り替え・変更する必要が生じる場合があります。
以下4つの状況における保険の切り替え・変更方法を解説します。
- 転職先の会社で新しい保険に切り替える
- 国民健康保険に加入する
- 加入していた保険を任意継続する(加入していた保険が健康保険、共済組合の場合)
- 配偶者の「被扶養者(家族)」に切り替える
転職先の会社で新しい保険に切り替える
新しい健康保険の資格取得手続きは、会社の人事部などの担当部門が行います。保険者(組合健保や協会けんぽ等)での手続きが完了すると、手元にあるマイナ保険証に登録されている情報が更新されます。
扶養家族がいる場合、その手続きも会社を通じて同時に進められます。
情報の更新には、資格取得日から通常2~5営業日、最大で10日程度かかることがあります。
この期間中に医療機関を受診する際、更新手続きが完了していないとマイナ保険証が利用できない場合があります。その際は、一時的に医療費を全額自己負担し、後日払い戻しを受けることになります。
国民健康保険に加入する
会社を退職したあと個人事業主になったり、非正規雇用で働いたりする期間がある、あるいは新たな就職先がない場合には、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険への切り替え手続きは、本人が行います。退職後14日以内に、居住している市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きを行います。
手続きに必要な書類のなかには、身分証明書のほか、退職証明書や離職票、健康保険資格喪失証明書があります。これらの書類は退職する企業に発行してもらう必要があります。発行には時間もかかるため、辞めることが決まったら早めに人事部門に依頼するようにしましょう。
また、必要書類は、各市区町村の役所によって異なる場合があります。事前に必ず確認しましょう。
加入手続きは多くの自治体で、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン申請が可能です。申請の対象や必要書類、具体的な手続き方法は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体の公式ウェブサイト等でご確認ください。
なお、扶養家族がいる場合、これまで扶養されてきた家族一人ひとりが国民健康保険に加入する必要があります。
その際、家族の届け出や保険料の納付は世帯主に行う義務があります。本人以外の手続きも忘れずに行いましょう。
加入していた保険を任意継続する
退職後も一定の条件を満たせば、最大2年間、加入していた健康保険を任意継続することができます。
任意継続の条件は、以下の2つです。
- 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること
(共済組合の場合は退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であったこと) - 資格喪失日(退職日の翌日等)より20日以内に申請の手続きをすること
この条件を満たせば、2年間の任意継続ができますが、気を付けなくてはいけないのが保険料の負担額です。
会社員の期間は、健康保険の保険料は社員と会社が折半で支払っています。会社を辞めた場合には、会社が負担していた分も含めた全額を自己負担することになります。
就職をした場合、保険料を期限までに納付しなかった場合など、任意継続期間であっても資格を喪失することがあります。
また、任意継続開始後2年間が経過すると自動的に資格喪失となり、国民健康保険への切り替えなどを検討する必要があります。
配偶者の「被扶養者(家族)」に切り替える
配偶者が会社員でその扶養に入る場合にも、保険証の切り替えが必要です。
保険への「被扶養者」の追加手続きは配偶者の勤務先の人事部門が行うため、会社に依頼します。
「被扶養者」となる本人が、加入していた社会保険の資格を失ってから原則5日以内に手続きする必要があります。手続きが完了すると、マイナ保険証に「被扶養者」として登録情報が更新されます。
この切り替え手続きが遅れた場合には、失効期間中の医療費は全額負担となることもあるため、注意しましょう。
あなたに合った
非公開求人をご紹介!
マイナビ転職エージェントにしかない
求人に出合えるかも。
あなただけの
キャリアをアドバイス!
マイナビ転職エージェントが
ご希望を丁寧にヒアリング。
シゴト性格や
強み・弱みをチェック
向いている仕事が分かる、
応募書類作成に役立つ!
AIと一緒に、
自己PRを作ろう
一人で悩まないで!
マイナビAI Pencilが自己PR文章を提案。
【まとめ】自分の加入している保険の種類・特徴を把握しておこう
公的医療保険には「健康保険(被用者保険)」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3種類があり、それぞれ保険料の計算方法、保障内容などが異なることを解説しました。
自分が加入している保険の種類や特徴を理解しておくと、転職や離職のタイミングなどで切り替えが必要になった際の手続きもスムーズです。近年ではマイナ保険証の導入やオンライン申請の普及により、手続きが簡略化されている部分も多いです。
これを機にぜひ、自分の加入している保険についていま一度確認するようにしましょう。
監修者

篠田 恭子(しのだ きょうこ)
特定社会保険労務士
おひさま社会保険労務士事務所 代表
1977年埼玉県川越市生まれ。システムエンジニアとして約10年勤務。仕事・子育てをしながら、2011年社会保険労務士試験に合格。2013年1月社会保険労務士事務所を開業。2014年4月特定社会保険労務士付記。2018年5月移転を機に事務所名を「おひさま社会保険労務士事務所」に変更。「働くすべての人が『楽しい』と思える職場づくりを応援します!」を経営理念に掲げ、地域の企業を元気にするために、日々活動している。
全国社会保険労務士会連合会、埼玉県社会保険労務士会、埼玉県社会保険労務士会 川越支部所属。
マイナビ転職 編集部
円満退職するために
退職前に知っておきたいワード
退職にまつわる疑問を解決しよう
-
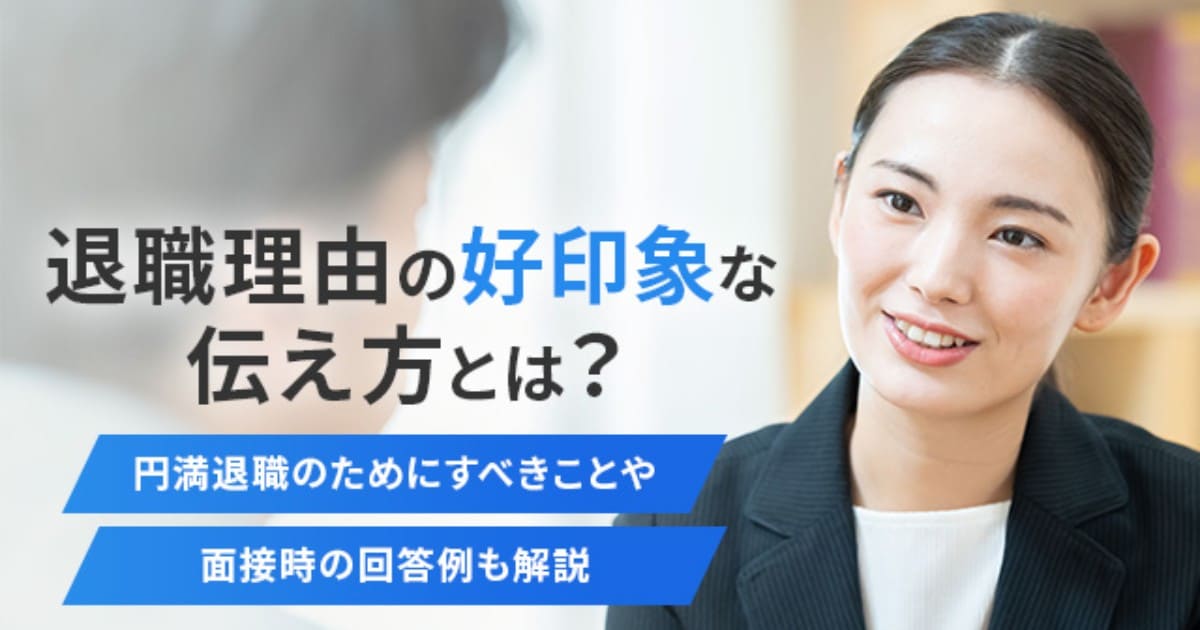
退職理由の好印象な伝え方とは?
-
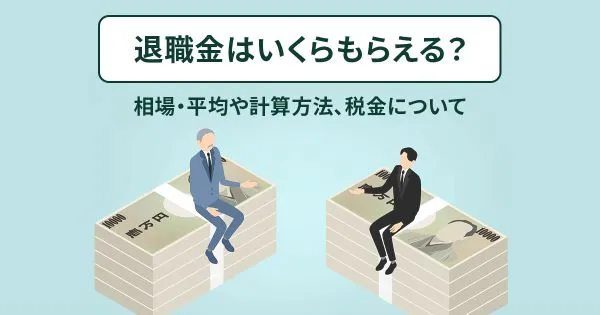
退職金の相場はいくら?
-

退職あいさつで好印象を残す方法
-
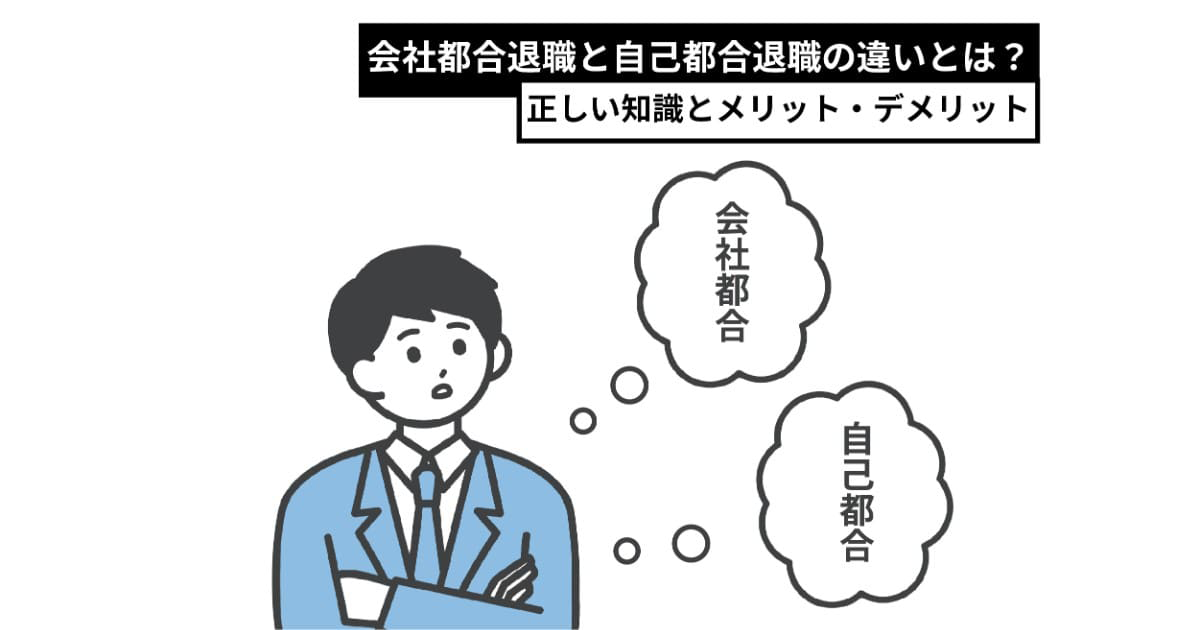
会社都合退職と自己都合退職の違い
-
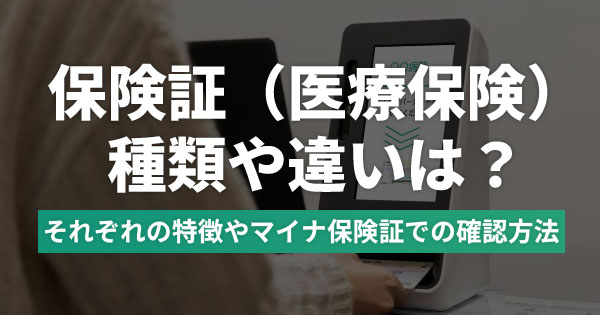
退職したら保険証はどうなる?
-
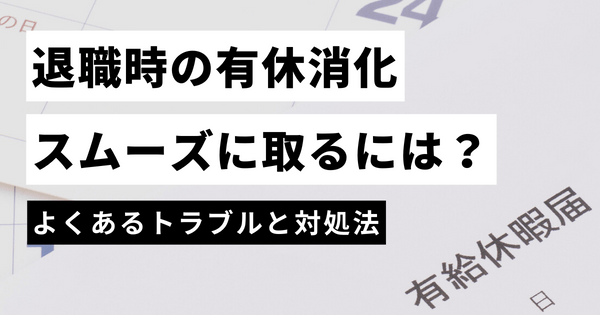
退職時の有給消化をスムーズに取るには
-
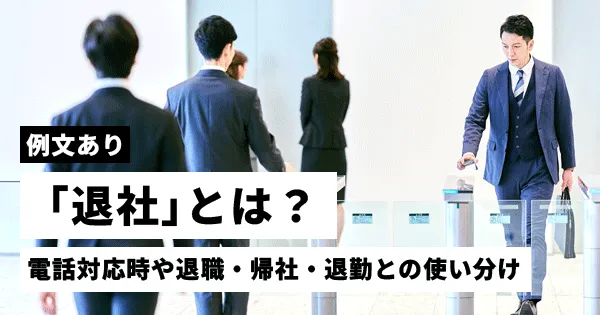
「退社」とは?退職との使い分け
-
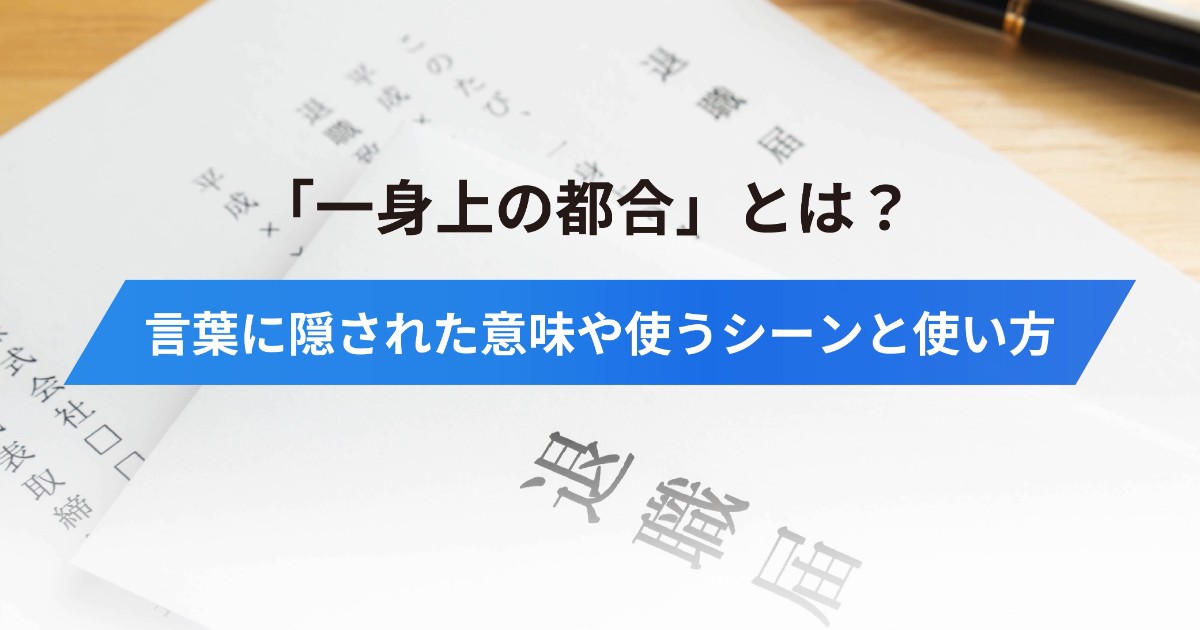
「一身上の都合」とは?
-

退職あいさつメールの書き方
-
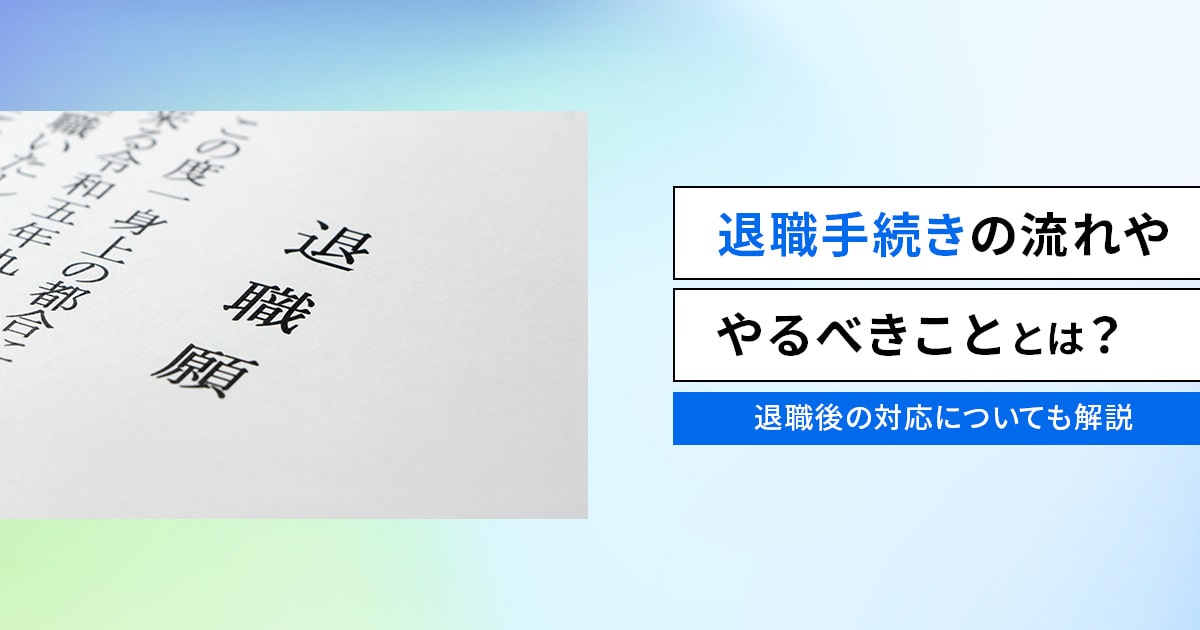
退職手続きの流れ、やるべきこと
-

転職後の住民税に要注意!
-

退職日は月末にしないほうがいい?
-

退職は何日前までに申し出るべき?
-

退職までにかかる期間は?
-

退職は2週間前の申し出でもできる?
-

転職したら退職金はもらえる?
-
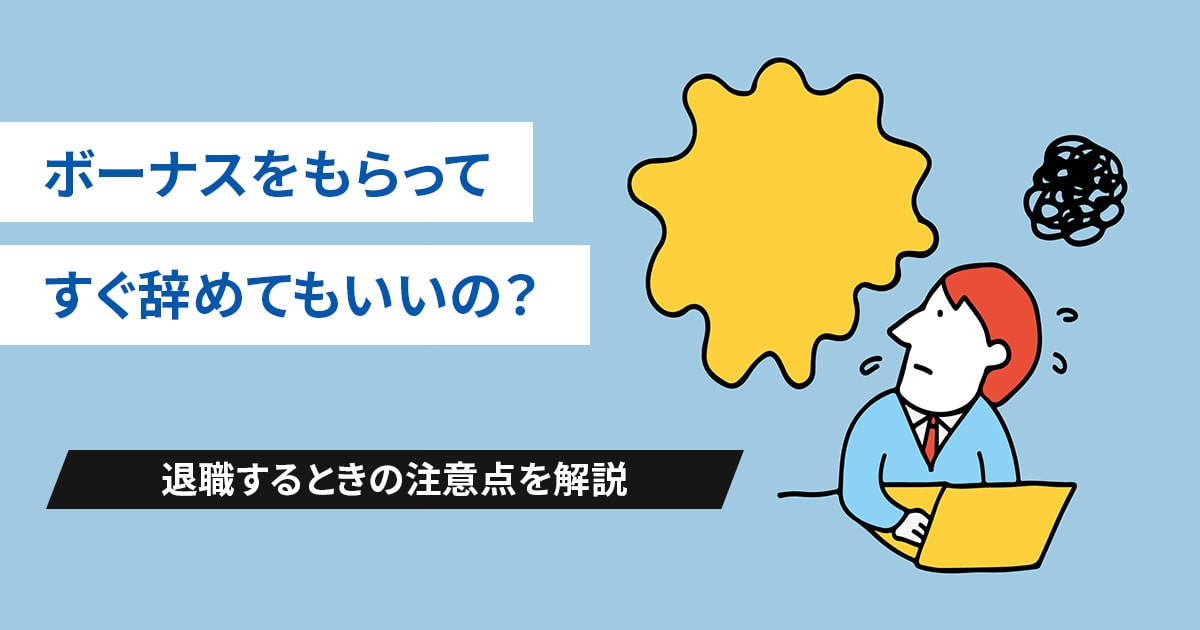
ボーナスもらってすぐ辞めていい?
-
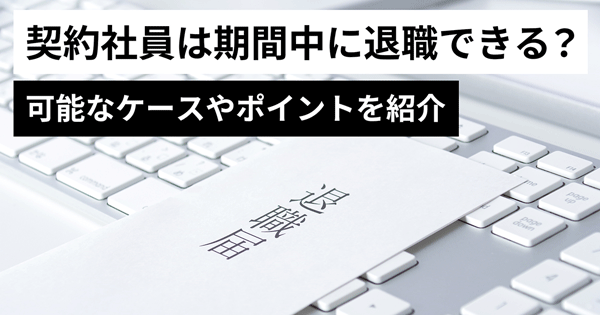
契約社員は期間中に退職できる?
-
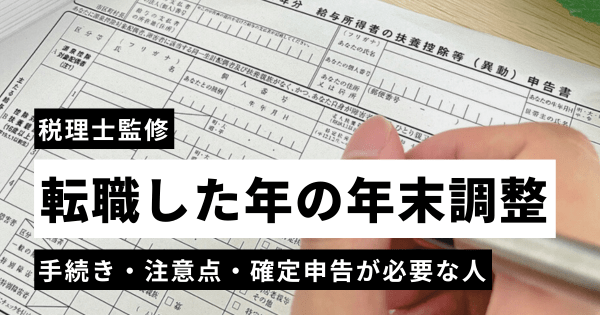
転職した年の年末調整
-
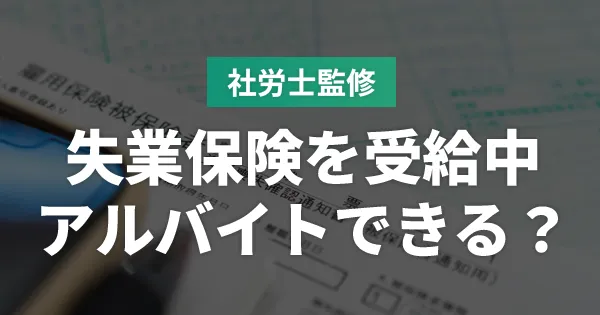
失業保険を受給中にアルバイトできる?
-
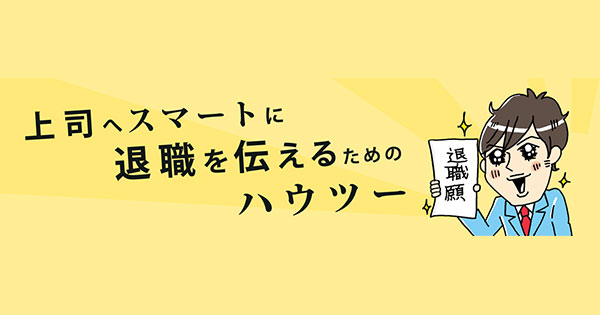
退職を伝えるタイミングはいつ?
退職届・退職願の正しい書き方
豊富な転職・求人情報と転職ノウハウであなたの転職活動を支援する【マイナビ転職】。マイナビ転職は正社員の求人を中心に“日本最大級”常時 約8,000件以上の全国各地の豊富な求人情報をご紹介する転職・求人サイトです。毎週火・金更新であなたの希望の職種や勤務地、業種などの条件から検索することができます。職務経歴書や転職希望条件を匿名で登録するとあなたに興味を持った企業からスカウトされるサービスや、転職活動に役立つ職務経歴書サンプルや転職Q&A、会員登録をすると専門アドバイザーによる履歴書の添削、面接攻略など充実した転職支援サービスを利用できる転職サイトです。